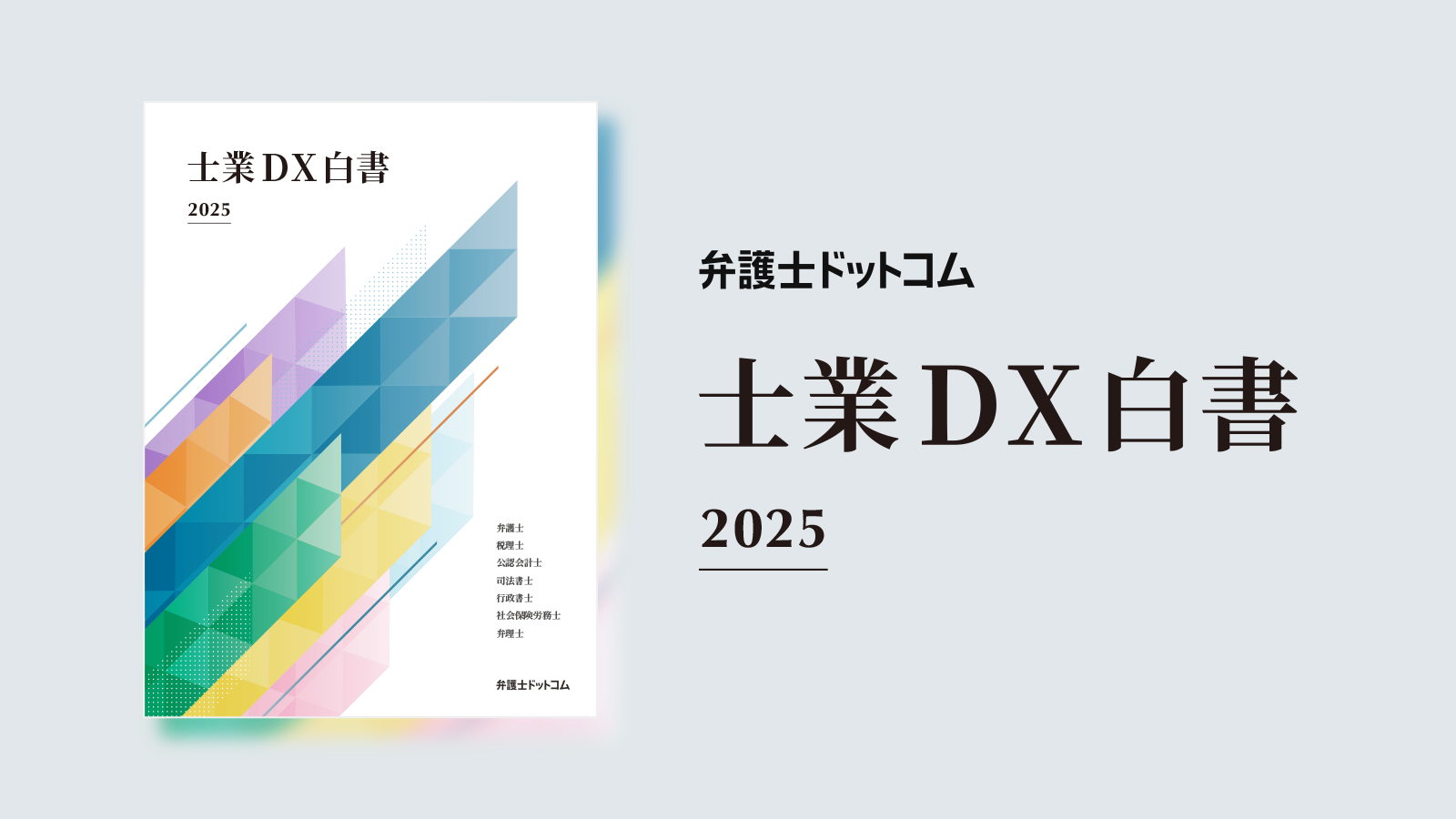オンライン商標登録で「紙はほぼゼロに」 cotobox社・五味CEO(弁理士)の野望
法律や会計分野におけるDXサービスは、生成AIの登場もあって、激しいスピードで進化を遂げている。この進化を担うのは、エンジニアだけではない。士業の当事者が自ら開発者として、先進的なサービスの開発に取り組んでいる。弁護士ドットコムの「士業DX白書2025」では、そんな士業当事者たちがどのような思いでサービス開発に取り組んでいるのかを聞いた。出願依頼をすると提携弁理士が出願書類を整え特許庁に提出してくれるオンライン商標登録サービスを提供しているcotobox株式会社の五味和泰・代表取締役CEO(弁理士)のインタビューを紹介する。(ライティング:国分瑠衣子)
「ワンフロア全部が紙」 世界共通の「包袋」問題
ーー起業のきっかけは何だったのでしょうか。
紙の多さです。転職し弁理士になってみて、とても紙が多いことに気付いたんです。
弁理士業界では、案件をまとめた書類の束のことを「包袋(ほうたい)」と呼ぶのですが、机の両サイドが包袋でいっぱいでした。特許権の存続期間は20年です。途中で裁判になる可能性もあり、書類をとりあえずとっておこうと、どんどん包袋が積み上がります。昔の案件を探すときにも事務員さんにお願いして包袋を探してきてもらっていました。
包袋の多さは世界共通の課題です。2011年にアメリカで知財系の専門家が集まるセミナーに参加したときに、シアトルの中心にある知財系法律事務所を訪問したんです。
超高層ビルの中にある事務所の執務室で「包袋が少ないですね」なんて話したら「じゃあ来るか」と下のフロアへ案内されました。ワンフロア全部がキャビネットで、開けると包袋がぎっしり入っていたんです。衝撃的でした。
もう一つの課題は費用感です。中小・零細企業に知的財産の見積もりを出すと「高い」という反応が多く、敷居の高さを感じていました。2014年にアメリカの大学院に留学したとき、リーガルテックが流行っていて、テクノロジーを使えば費用を下げられるし、業務効率化できると気付きました。帰国して事務所を辞め2016年2月にコトボックスを立ち上げました。
ーー起業に対し、周囲の反応はどうでしたか。
あまり賛成されませんでした。「せっかく自費でアメリカ留学して学位をとってきたのだから、弁理士としての仕事で回収したほうがいい」などと言われましたね。
それでも起業できたのは、帰国直後の勢いがあったからです。向こうでスタートアップにチャレンジする人たちのコミュニティーに入っていて、スタートアップの作り方を議論したり、夢を語ったりと非常にいい影響を受けました。通っていたロースクールよりも居心地がよかったぐらいです。
だから「自分にも起業できる」というマインドがありました。帰国後、事務所に復帰して働いていたら、きっと熱がさめて、こううまくはいかなかったと思います。スタートアップで世界を変えてやるんだという勢いが、人生の転機になりました。
ーーコトボックスのビジネスモデルは五味さんが考えたのですか。
ウェブで集客して、ユーザーが商標検索でき、商標登録を決めた段階で料金をいただくというスキームは僕が考えました。でも、問題はそのシステムを誰がつくるかですよね。
当時僕はエンジニアではなく、つながりもゼロでした。だから渋谷にあるプログラミングの学校に入りました。先生や周りと話しているうちに、エンジニアの人たちの好きな話題が分かり、仲良くなりました。コトボックスのサイトは学校で出会ったエンジニアに作ってもらったんです。
ーーサービスの立ち上げは順調でしたか。
2016年2月に会社を設立して、サービスをローンチするまでは1年半ぐらいでした。エンジニアが、僕が思っていることを要件定義してくれ、朝から夜まで、ああだこうだといいながら開発しました。お金はありませんでしたが楽しかったですね。
当時の検索精度は自分が十分満足できるものではなかったのですが、折り合いをつけてローンチしました。僕はプロの弁理士としてやってきたので、もっと完全な形でないと出したくないなという葛藤はありました。でも、検索できるという新鮮なユーザー体験が大事だったようで、結果としてあのタイミングで出して良かったです。
ーーコトボックスを使えば、紙はゼロになるんでしょうか。
特許庁からのやり取りの一部で紙は残りますが、それ以外はありません。企業と弁理士の間ではゼロで、包袋は存在しません。識別しやすいようにPDFやWord、メールも使わず、システム内に全て情報として格納されます。
知財とAIは好相性 フル活用で専門家にしかできない仕事を
ーーユーザーは中小企業が中心ですか。サービスの差別化ポイントも教えてください。
特許庁に出願されている商標のうち4.8%のシェアをとっています。中小企業を分母とした場合は9%ほどで、10社に1社ぐらいはコトボックス経由です。コロナ禍で認知度が一気に上がりました。
特徴はカスタマーサポートの人員を配置している点です。問い合わせにすぐ対応できますし、日々UI、UXを改善しています。AI時代だからこそ、人とのコミュニケーションは大事だと考えています。
お客さまとの膨大なテキストコミュニケーションのデータの多さも強みです。今後、チャットボットなどをつくるときに、専門領域のデータを持っていることは大きいです。
2023年からグローバル対応の商標業務効率化サービスをスタートし、イオン株式会社で導入が決まりました。中小企業から大企業まで幅広いサービス提供ができるようになります。こうした対応の幅の広さは他ではやっていないと思います。
ーー生成AIと知財は相性がいいでしょうか。
知財は文書の世界で、生成AIは文書生成や要約が得意なので相性はいいですよね。特許出願の前に、過去に同様の技術の文献や論文が出ていないかチェックする必要があるのですが、これらのドキュメントをすべて読むのは大変です。生成AIで差分を調べることも簡単になりそうです。
また、特許庁で審査官とやり取りするときに文章を書くので、生成AIでの編集をたたき台にすれば、作業量は2分の1ぐらい、それ以下になっていくでしょう。
ただ、問題は精度です。精度が少しでも甘くなると、専門家は違和感を持つのでその折り合いをどうつけるかが課題だと思っています。今のところは類似のサービスも含めて、生成AIが文章のたたき台や差分チェックを行い、専門家が補正して品質を担保するというパターンがほとんどではないかと思います。
コトボックスでも申し込み後は提携弁理士が引き受けています。弁理士に代わって業務のすべてをAIに任せられるかを検討したこともありましたが、早々にあきらめました。やはり最後は人間なのだと思います。
ーーAI時代の専門家の役割は何だと考えますか。
弁理士業界は平均年齢が高く、優秀な人がこなくなったと言われています。しかし、AIが進化しても最後の品質担保と依頼人とのコミュニケーションは人間がやる価値があり、それが専門家が生き残る道ではないでしょうか。
それと、弁理士はもっと守備範囲を広げたらいいのかなと思います。取引先である企業の担当者は商標専門ではなく、他の領域も兼務していますよね。他の分野のコミュニケーションもとれる幅広い知識やネットワークがある人が活躍できます。コンサルティングはその好例でしょう。
そのためにはテクノロジーをフル活用する必要があります。その意味では、専門領域ほど属人性が高くなる業界なので、ナレッジシェアや情報の標準化がもっと必要だとも思います。
ーー起業を考えている士業の人にメッセージをお願いします。
士業は専門知識があるので優位なポジションにいると思います。それに僕が起業したときよりも国の起業支援も進んでいるのでぜひチャレンジしてほしい。何より、自分の事業ドメインを軸に起業すると、熱量が維持しやすいと思うんですよね。僕はデザイナーのコミュニティーにも入っていますが、ぜひいろいろな業界の人ともつながって視野を広げてほしいです。
【Cotobox(コトボックス)】
「人と知財を結ぶ」「知財を誰もが平等に取り扱えるようにする」をミッションに、2017年から始まったオンライン商標登録サービス。フォームにネーミングやカテゴリなど必要事項を入力すると、AI検索機能で似た商標がないかを簡易チェックできる。そのまま出願依頼すれば、担当の提携弁理士が出願書類を整え特許庁に提出してくれるため、人的・金銭的なコストの削減になる。2023年には侵害検知や海外への出願などに対応した「Cotobox商標管理クラウド」もリリースした。
【プロフィール】
五味和泰(ごみ・かずやす)
cotobox株式会社代表取締役CEO。早稲田大学理工学部卒業後、大手建設会社を経て、2009年に弁理士登録。南カリフォルニア大学で法学修士号を取得後の2015年、はつな知財事務所(2022年にAuthense弁理士法人に名称変更)、2016年にCotoboxを設立。同サービスは2021-2024年の特許庁への出願取扱件数が国内1位となっている。
【お知らせ】
「士業DX白書2025」では今回のような開発者インタビュー以外にも、弁護士、税理士など7士業を横断した、DX期待度スコアの算出、士業ごとの概要・課題分析、士業やそのユーザーのアンケート、DXサービスリストの作成など、多岐にわたるコンテンツを掲載しています。PDF版を無料で配布していますので、ぜひご一読ください。
詳細はこちら