【士業の生成AI活用最前線】書面作成はお手のもの、債務整理や離婚の陳述書づくりを大幅短縮
ビジネスの現場では、生成AIをいかに業務に組み込むかが大きな課題になっています。一方、正確性などにはまだ不安が残り、仕事の性質上、業務利用をためらう士業も多いようです。 現状のレベルでどんなことができるのか。士業のAI活用の最先端を取材していきます。
●AIでつくれる書面のレベルは?
前回に続き、話を聞くのは司法書士の2人。日本最大級の「司法書士法人みつ葉グループ」の宮城誠代表(写真上)と、士業の集客や業務効率化を支援する「株式会社スタイル・エッジ」の島田雄左社長(写真下)です。今回はより士業の業務とかかわりが深い、書面の作成についてみていきます。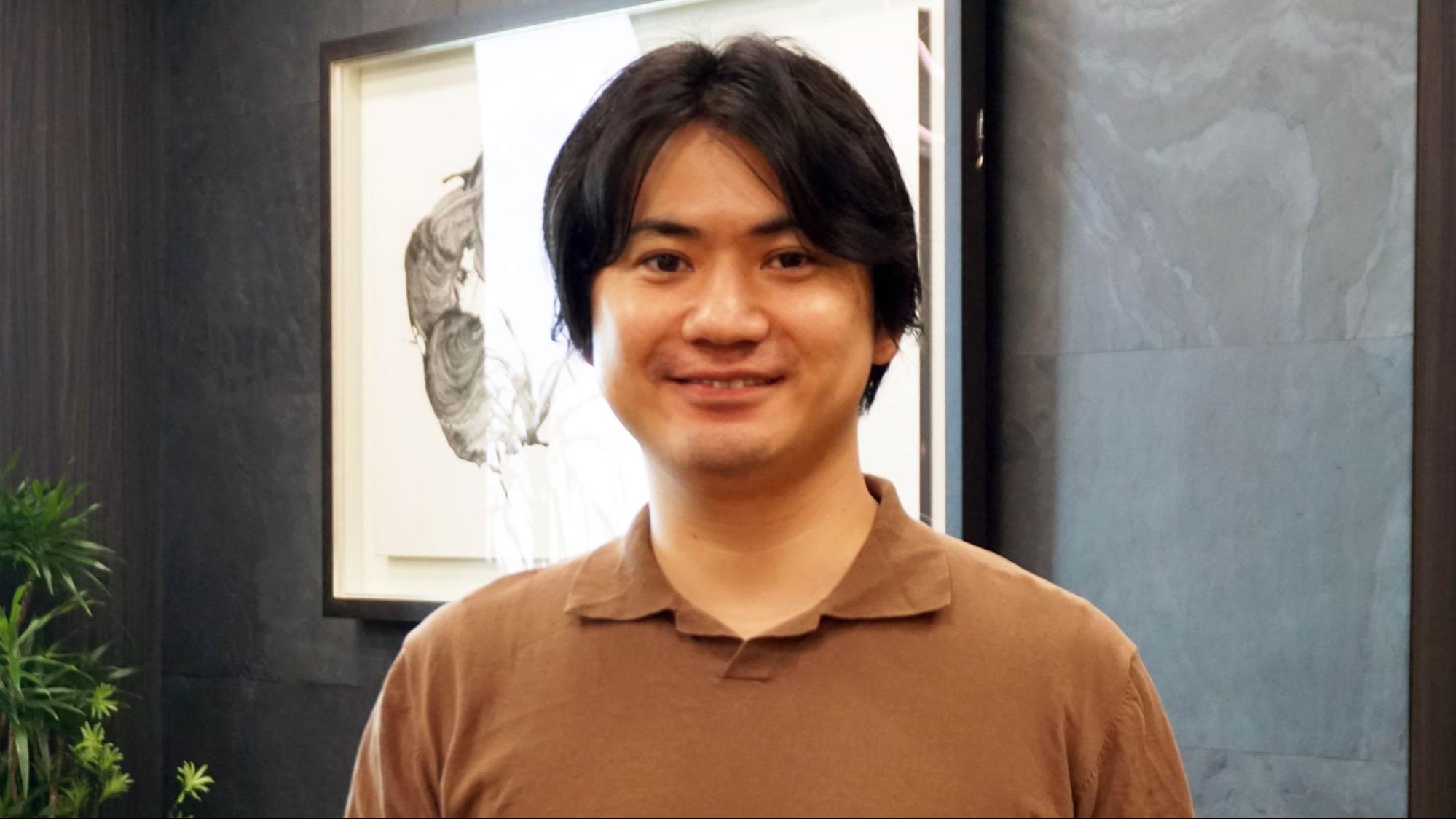

●文字起こしや調査票から陳述書を生成
生成AIに書面をつくらせることに不安を感じる士業は多いと思います。しかし、書面の種類によっては、現状でも業務効率を上げられる可能性を秘めています。
たとえば、みつ葉グループでは、依頼者の自己破産手続きの際に、裁判所に提出する陳述書のドラフトを、生成AIを活用してつくっています。法的な主張ではなく、破産申し立てに至る事情という経緯・ストーリーをまとめるので、生成AIが有効というわけです。
宮城代表「債務整理で時間のかかる業務の1つで、事務所によってどの要素を入れるかなど、細かなニュアンスも異なります。パラリーガルがつくり、資格者(司法書士や弁護士)がレビューするという工程を繰り返すと対応できる件数が限られるので、初めから適切なニュアンスを含んだ書面をつくれたらいいのに、と思っていました」
そこでスタイル・エッジは、あらかじめプロンプトを設定しておける「GPTs(ChatGPTの場合)」の機能を使い、ドラフト作成の仕組みを整えました。
前回紹介したように、みつ葉グループでは電話相談などの内容を録音・文字起こししています。また、依頼者から返ってきた取引履歴などもデータ化し、「債権調査票」にまとめています。
これらのファイルをGPTsにアップロードすれば、いつごろ、なんのために借り入れをして、どうして返済ができなくなったかというストーリーが自動で書き上がります。
宮城代表「点数をつけるとコンスタントに80点ぐらい。そのままでも使えるレベルのものが出てきます。細かい部分を修正して完成させますが、最初からつくるより断然早い。これまで30〜60分かかっていた作業が5分で済みます」
GPTsを通すことで、担当者による品質の差もなくすことができたといいます。
●離婚や交通事故など幅広く活用可能
では、GPTsの設定(プロンプトの作成)にあたって、どんな工夫をしているのでしょうか。
島田社長「1つあげるなら、作例として今まででピカイチの書面を参照させることで精度を上げている点です」
どういう情報から、どういう書面をつくればいいかの理想形を示すことで、品質を上げているのだそうです。
島田社長「このGPTsを応用すれば、債務整理以外の分野の書面もつくれます。たとえば、離婚案件。支援をしている、ある法律事務所では、依頼者に『どうして離婚しようと思ったのか』や『どんな結婚生活だったのか』などを箇条書きで入力してもらうことで、弁護士が陳述書作成にかかる時間を大幅に減らしています」
機微な情報を含むことも多いので、利用するAIサービスについては規約の確認や設定により、入力情報が学習されないようにすることも重要です。
現在、スタイル・エッジでは交通事故の分野についても同種の試みができないか、支援先の法律事務所と実験を進めているといいます。
島田社長「今後は依頼者も事前に生成AIを使ってくることが考えられます。AIの回答とかけ離れたものが出てくると『ちょっと違うな』と思われてしまう可能性があるので、専門家側もAIをうまく活用できていると、依頼者ともいい関係をつくれるんじゃないかと考えています」
今回紹介したのは、高度な法的専門性は必ずしも必要とされない文書作成でした。より専門性の高い業務に生成AIは使うことはできるのか、次回以降はそのあたりも探ってみたいと思います。
