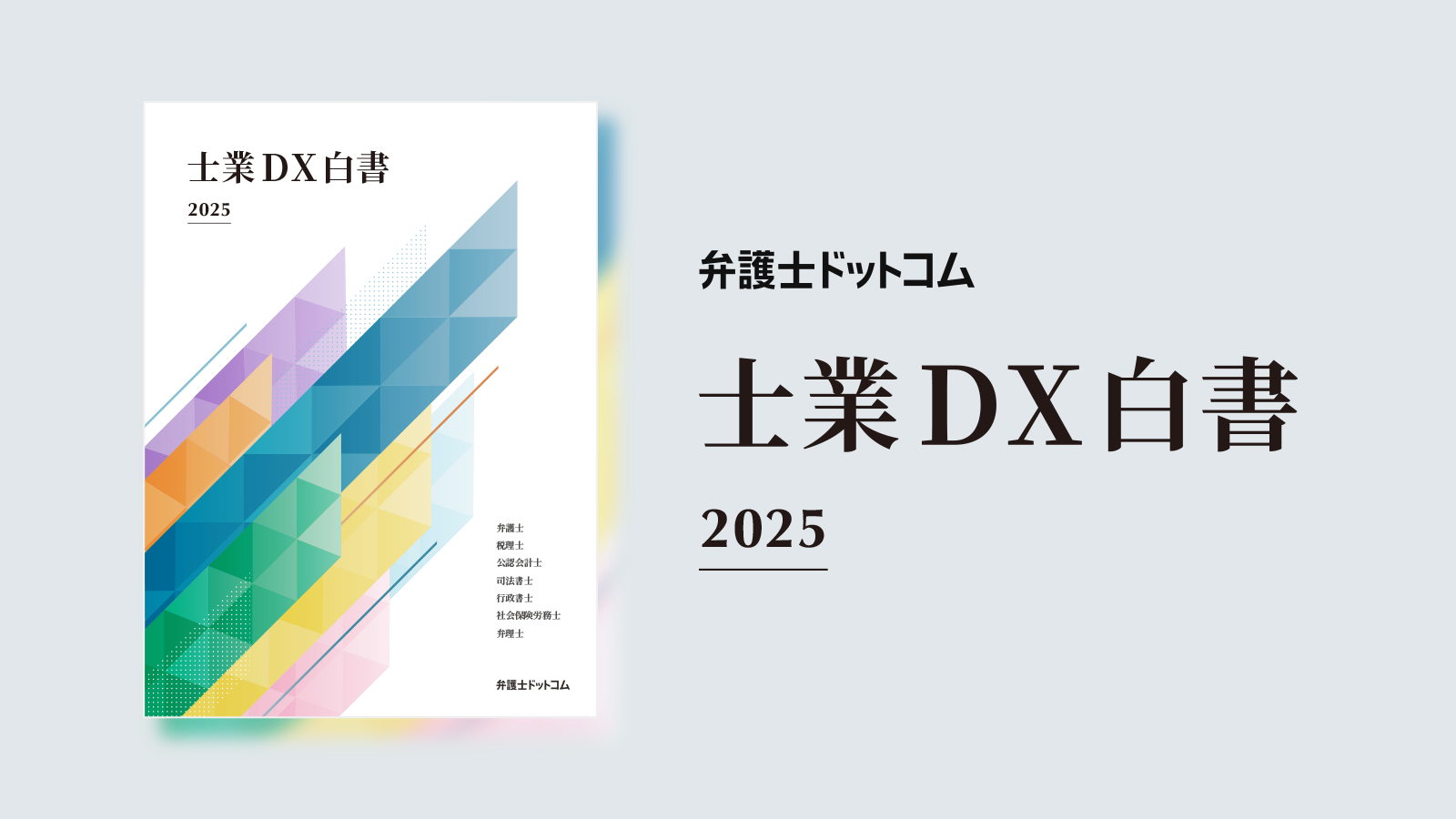「申告書を出すだけの士業は終わる」 ROBON・荻原氏(税理士・公認会計士)が語る本質論
法律や会計分野におけるDXサービスは、生成AIの登場もあって、激しいスピードで進化を遂げている。この進化を担うのは、エンジニアだけではない。士業の当事者が自ら開発者として、先進的なサービスの開発に取り組んでいる。弁護士ドットコムの「士業DX白書2025」では、そんな士業当事者たちがどのような思いでサービス開発に取り組んでいるのかを聞いた。税務に関する相談をチャット形式で即時に回答するサービスを展開する株式会社ROBONの荻原紀男・取締役CSO(税理士・公認会計士)のインタビューを紹介する。(ライティング:国分瑠衣子)
4割の時間を削減、税務・労務のセットで税理士をサポート
ーーROBON設立のきっかけを教えてください。
40年近く公認会計士と税理士をしています。2000年にIT業界に入り、ソフトウェア協会の会長をしていた2018年にがんで入院したんです。病室で横になっていたときに、データを効率的に活用すれば、税理士は四半期決算の申告書づくりで苦労しなくてもいいのではとひらめいたことがきっかけです。
税理士の仕事で時間がかかるものは2つで、決算申告書の書類作成と税務相談です。最近でこそ中小企業のDXは進んでいますが、当時は顧客企業のDXが遅れていたため、データ連携できない問題がありました。いまも紙の現金出納帳と領収書を送ってくる会社もあります。税理士の生産性を上げたいと、立ち上げました。
ーー法人税申告書を自動作成する「決算ロボット」「申告ロボット」の特徴は何でしょうか。
どんな会計ソフトにでもAPI連携(異なるシステム間でデータをやり取りする仕組み)ができる点です。これまでは会計ソフトと申告書ソフトの間のAPI連携がほとんどとれませんでした。決算ロボットなら、決算書の値の転記、会計ソフトに登録するルールを覚えさせると、ソフトのデータから必要な情報を取り出して連携でき、簡単に四半期決算が終わります。
ーー税務相談も時間がかかるんですね。
お客さまの質問レベルが高いと、調べるのに数時間かかります。検索サイトでキーワード検索し、一つ一つ引っ張って回答を出さなければならないことが課題でした。
そこで生成AIが出たときに「これを使えばチャット形式で税務相談ができる」と、生成AIに六法、税法、省庁の通達などを読み込ませたんです。
開発の過程では、情報に序列をつくる「データの重みづけ」に苦労しました。ただ、データを読み込ませているうちに回答精度が上がり、2024年1月に「税務相談ロボット」、2024年4月には「労務相談ロボット」を提供開始しました。地方で開催する税理士会のDX相談会に行くと、他社のクラウド会計ソフトの中で異色なので、面白がってもらえます。
ーー税務・労務相談ロボットでどれぐらいの時間削減ができるのですか。
だいたい4割ぐらいの時間削減ができます。ただ、難しいのが売り方です。普通に考えると、労務相談が1カ月50件もある会社ってブラックじゃないですか。そうした会社はロボットを買いませんよね。だから一問300円で販売し、誰でも相談できる国民のAIにしたいと思っています。2024年の10月には、スポットで都度課金できる一般従業員向けのプランも始めました。
ーー税務相談ロボットのユーザーは主に税理士ですか。
大手税理士法人が多いですが、一般企業や金融機関にも使っていただいています。自社のデータを載せてOEMで提供してほしいというオーダーもあります。最近は自治体からの問い合わせが増えています。確定申告の時期に、税務署ではなく役所の窓口にも相談がたくさんきて、さばききれないので何とかしたいというニーズです。
地方の税理士からは「税務相談は少ないけれど、労務相談がとても多い」という声もあります。相談先がわからず、身近な税理士に相談するのだと思います。税理士の方々には「税務相談ロボット」だけなく、「労務相談ロボット」も活用してほしいです。
申告書を出すだけで士業と言われる時代を終わらせたい
ーー相談ロボットは、税理士法で規制対象になる「非税理士」にあたるという問題はなかったのでしょうか。
税務相談ロボットを出すときに国税庁に相談すると、回答に出典が明記されていれば、検索エンジンと同じなので、税理士法には抵触しないということでした。ただし、出典を出さなければ触れるということでした。労務相談も同じですね。
ーー税理士業界は高齢化が深刻です。課題は何でしょうか。
年々受験者数が減り、「うちの県は今年3人しか受からなかった」という話も聞きます。ベンチャーブームで企業数は増えていますが、税理士は足りない。採用ができず、顧客を断るか合併するかという深刻さです。
税理士の生産性を測る分かりやすい指標は、1人あたり何社担当するかです。どこに時間を使っているのか調べ、業務効率化しなければなりません。別の言い方をすれば、DXをしなければ淘汰されてしまいます。
高齢化については、団塊の世代とその下の世代では意識の差があるのではないでしょうか。下の世代はDXをしないとやっていけないことは理解しています。
ーー決算ロボットのような商品が出ることで「税理士の仕事がなくなる」という見方があります。
新しいことを学ぶ意欲のある税理士には脅威にならないと思います。企業が決算・申告ロボットを使っても、税理士に最終確認を求めると思いますし、「税務相談ロボット」でも個別の判断には税理士が必要です。それにロボットは法律でグレーな部分は答えられないので、それも税理士の出番です。
考えてみてください。弁護士は訴状をつくって裁判所に提出し、それから法廷で戦いますよね。でも、税理士は申告書を作成し、税務署に出して終わりです。申告書をつくることが目的という、こんなレベルの低い目的はありません。私はそれを士業と言って偉そうにする時代を終わらせたいんです。
中小企業が申告書を書けないことを理由に、お金をとってきただけでしょうと言いたいです。中小企業が自ら申告書を書けるようになったら、どうするのでしょうか。
日本企業の99.7%が中小企業で、それがこの国を衰退させている。中小企業のあり方を変えてこなかった税理士にも責任がある。中小企業を大企業にして、強くする。それがこの国の未来をつくると信じています。
ーー生き残るために税理士が学ぶべきことは何でしょうか。
コンサルティング能力です。経営に関する幅広い知識を持ち、お客さまの労働時間を分析し、減らせるところはないか考えて、業務効率化する助言ができるかだと思います。
ーーDXを進める上で、行政の側も変わっていかなければなりません。
国税庁で言えばかなりDXが進んでいて、税務調査の件数はすごく減っているんです。人が減っていくということは、否が応でもDXを進めなければならないので、悪いことではないと思います。
ーー公認会計士、社労士など他の士業の今後をどう見ていますか。
弁護士のように法廷闘争があり、証拠の価値をどれだけ強くみせられるかはまだまだAIでは代替できないでしょう。一方、公認会計士は厳しいですよね。AIで監査は業務効率化されています。不正などが発生しないような内部統制は人間が作る必要がありますが、監査コストは削減されてしまうので、収入は減るかもしれません。司法書士や行政書士は文書が定型なので、そうした人たちがいなくても進められるような行政の在り方にしなければなりません。
ーー税務相談ロボットをどう進化させますか。
回答の精度を上げて、複雑な質問にも答えられるようにします。データが増え、法体系を守るなどのメンテナンスコストを考えると同業他社はついてくることができません。クラウドの料金も上がってきているので、うちしかデファクト・スタンダードにならないと思うんですよね。私は借金を気にしないんです。失敗ってやめたら失敗だけど、やり続ければ失敗にはならないです。きれいに勝とうと思わず、攻め続けます。
【相談ロボットシリーズ】
税務に関する相談をチャット形式で即時に回答する「税務相談ロボット」と、労務問題を相談できる「労務相談ロボット」を展開している。税務相談ロボットについては、税務について質問すると、出典の明示とともに、要約した文章を回答する。質問できる対象税目は法人税、所得税、消費税、相続税、地方税で、税理士・公認会計士だけでなく、企業の財務・経理担当者や個人事業主、個人も活用できる。労務相談ロボットも、士業や企業の人事労務担当者、従業員まで幅広くカバーしている。
【プロフィール】
荻原紀男(おぎわら・のりお)
株式会社ROBON取締役CSO。中央大学卒業後、外資系会計事務所及び監査法人を経て、荻原公認会計士税理士事務所を開業。 2000年、株式会社豆蔵(現 株式会社豆蔵ホールディングス)を創業、2003年、同社代表取締役社長に就任。現在は株式会社豆蔵 K2TOPホールディングス 代表取締役会長兼社長。子会社である株式会社ROBONの取締役。
【お知らせ】
「士業DX白書2025」では今回のような開発者インタビュー以外にも、弁護士、税理士など7士業を横断した、DX期待度スコアの算出、士業ごとの概要・課題分析、士業やそのユーザーのアンケート、DXサービスリストの作成など、多岐にわたるコンテンツを掲載しています。PDF版を無料で配布していますので、ぜひご一読ください。
詳細はこちら