ChatGPTで浮き彫りになる弁護士業務の本質 法律事務所での活用のすすめ
全世界で大きな話題を引き起こしたChatGPTの登場から1年超が経過した。ただし、法律文書の作成はまだ難しく、しばらく触っていなかったり、一度も触れたことがなかったりというケースも多いのではないだろうか。 2023年11月に『法律事務所のためのChatGPT利活用ガイドブック』を上梓した寺島英輔弁護士(写真右:東京フィールド法律事務所、60期)、小谷野雅晴弁護士(同左:神楽坂総合法律事務所、73期)は、それでも業務での活用法を試行錯誤したほうが良いと強調する。くわしく聞いた。 (弁護士ドットコムタイムズVol.70<2024年3月発行>より)
⚫️なぜChatGPTは不完全なのか
ChatGPTはなぜ法律文書の作成が苦手なのだろうか。寺島氏は次のように説明する。
「もう有名な話ですが、ChatGPTはプロンプトを前提に次に続く言葉を統計・確率的に予測して文章をつくります。一度間違いが生じても後戻りできず、最後まで文章を出し切ってしまうのです」
こうした単線型の仕組みの結果、推論能力の弱さや、まことしやかなウソをつくといった欠点が指摘されている。また、過去のデータに縛られるため、社会や経済の変化に即した問題に対応することも難しい。
これに対して、弁護士がおこなう法律文書の作成には、解釈・評価・規範的判断といった複雑な工程が必要となり、ときには証拠に基づき主張を修正するなど、複数の選択肢を行きつ戻りつしながら大局的な判断をすることも求められる。
最新の研究では、こうした思考法をツリー構造に置き換えて再現しようとしたり、単線型の仕組みの中にフィードバック機構をつけて弱点を克服しようとしたりする試みもおこなわれているそうだが、まだ生成AIが法律文書を書くには時間がかかるようだ。
⚫️なぜ使ったほうが良い?
ただ、二人は「完全じゃないからといって、使わないのはもったいない」と口をそろえる。「未熟」な技術だからこそ楽しみや気づけることがあるのだという。
「ほとんどの弁護士が生成AIを使うようになる頃には、インターフェースは洗練され、プロンプトを工夫しなくても良いものが出てくるようになっていると思います。でも、言い換えれば生成AIがどういう処理をしているか分かりづらくなる」(寺島氏)
今のうちからChatGPTなどに触れ、生成AIの仕組みやどういう間違いが起こりやすいかを肌感覚で知っておくことが、将来使う際に役に立つという。書籍でも最新の研究論文を数多く引いて、ChatGPTの仕組み解説に力を入れている。
また、生成AIに対する理解が深まれば深まるほど、弁護士業務の本質的な部分が見えてくるという。
「生成AIの研究は、脳の構造の研究と相互に関係しあっているようです。たとえば、弁護士が日常的におこなっている法的推論がどういう要素から成り立っているかを調べることで、現在のChatGPTの仕組みではなぜ精緻な法律文書をつくれないのかの研究が進みますし、逆に現在のChatGPTが出す応答の傾向を調べることで、弁護士の法的推論の理解も進むというようなことがいえると思います」(寺島氏)
業務で使おうとすれば、法律事務所での仕事がどういうタスクの集合体かを考えざるを得なくなる。ChatGPTを仕事に組み込むことは、業務の因数分解につながり、効率化のヒントが得られたり、弁護士が何に注力すべきかが明確になったりする効果もあるのだという。
⚫️現状でも法律事務所で活用法ある
では、二人はChatGPTをどのように活用しているのか。まず、ともに挙げたのが翻訳。指示をすれば要約もでき、短時間で内容を大づかみできる。執筆にあたり、海外文献を大量に読み込む際にも重宝したという。
続いて、ブレーンストーミング、いわゆる壁打ち相手にするという方法だ。事件処理で悩んだ事実認定上の問題や法律上の問題を入力し、その応答をヒントに思考を深めていく。ChatGPTの答えが必ずしも役に立つわけではないが、自分の思考を整理し、言語化するという過程が重要なのだという。壁打ちという点では、交渉や尋問などのトレーニングにも活用できるそうだ。
ちなみに『法律事務所のためのChatGPT利活用ガイドブック——仕組みから解き明かすリーガル・プロンプト』という書籍タイトルも、こうした手法で出した複数候補の中からベースを選び、微調整して決めたという。
また、弁護士は法律のプロフェッショナルであると同時に、依頼者に対応するサービス業でもある。しかし、司法試験で接遇スキルは問われない。ChatGPTは法律文書の作成は苦手でも、自然なテキストはお手のものだ。依頼者に寄り添って励ましたり、説得したりする文言を考えてもらうのも良いという。調査・統計の分析やまとめに使う方法もかなりの時間短縮になる。
「たとえば、会務などでとったアンケート結果をまとめたいとき、ChatGPTに命令すれば、表や分析結果がすぐに出てきます。特に若手には使えるテクニックじゃないでしょうか」(小谷野氏)
このほか、小谷野氏の事務所では広報用SNSアカウントに投稿する際のリード文をChatGPTに考えさせているそうだ。書籍では、守秘義務や著作権など活用する際の法的問題からzero-shot、few-shot、Plan-and-Solve、思考の連鎖(Chain of Thought)などプロンプトの基礎知識、弁護士業務で使える具体的なプロンプト例などもまとめた。
⚫️生成AIと弁護士のこれから
2025年からは民事判決情報がオープンデータ化する見込み。取り込める法律情報が増え、技術的な改良も進むことから生成AIの出力はますます精緻化していくと考えられる。今後の業務にどういう影響があるか不安に思う弁護士も多いだろう。しかし、二人は弁護士の業務自体が劇的に変わるとは考えていないという。
「少なからず業務は効率化するので、生成AIを使いこなせる弁護士のほうがより他の部分に能力と時間を割ける分、有利になるのは間違いないでしょう。ただ、専門分野以外については出力されたものの正しさを判断できません。使える領域は限られるし、その領域で出力内容の正誤を判断する能力がないと弁護士業務はやれないと思います」(小谷野氏)
「たとえば、準備書面を書く際、そのベースとなるデータを入力する必要があります。入力すべきデータを選別する段階で、すでに弁護士の専門的な能力が必要になります。証拠との対応関係や法律論など、悩みながら法律書面の起案をすることで、事件に対する理解が深まっていく面もあります。単なる省力化、業務効率化と考えるのではなく、自分の思考や専門性を深めるトレーニングツールとして活用するのが良いと思います」(寺島氏)
業務効率化や自己鍛錬の道具として生成AIを使わないのはもったいないと感じる一方で、経験や知識が不足している分野で身の丈を超えて生成AIに依存するようになると、大きなミスをしでかしてしまったり、弁護士としての実務能力の向上が止まってしまったりする懸念もあるという。生成AIとの付き合い方の勘所をつかむという意味でも、無料版で良いから利用を継続してみることは有効と言えそうだ。
弁護士業界内ではまだ、生成AIについての情報交換の機会があまりないという。今回の出版をきっかけに、活用法について議論を深めていきたいとも語った。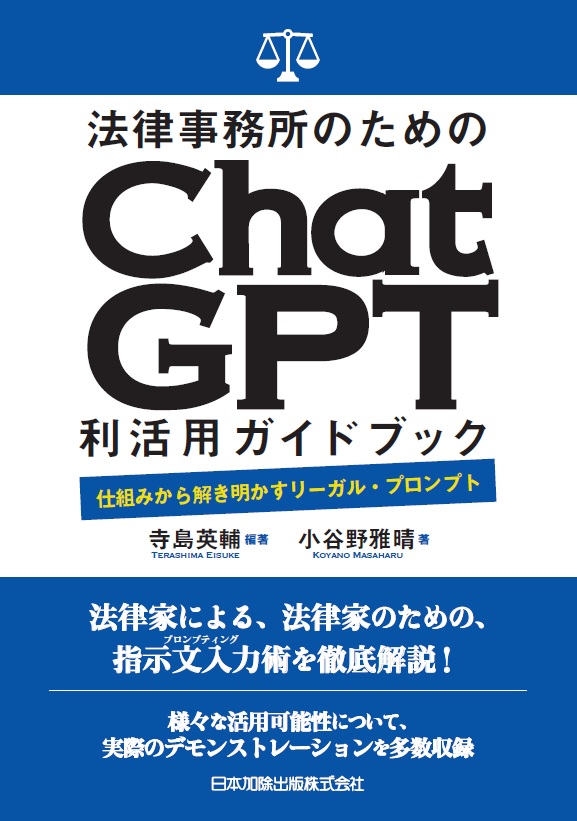
『法律事務所のためのChatGPT利活用ガイドブック 仕組みから解き明かすリーガル・プロンプト』
寺島英輔・編著/小谷野雅晴・著
日本加除出版/発行・2023年11月
2,750円(税込)
