刑事弁護に「唯一の正解はない」、日々が「学び」 櫻井光政弁護士インタビューvol.2
数多くの刑事事件を手がけながら、新人弁護士の養成にも力を注いでいる櫻井光政弁護士(第二東京弁護士会)。養成の様子を事例とともに紹介する著書「刑事弁護プラクティス」シリーズ(現代人文社)は、2013年の初版発行以来、法曹関係者に注目されている。 櫻井弁護士は、刑事裁判官を主人公にしたフジテレビ系月9ドラマ「イチケイのカラス」(2021年4月〜放映中)の原作となった同名コミック(作:浅見理都、講談社)では、法律監修も務めた。 2回目は刑事弁護に取り組むうえでの思いについて、紹介する(インタビュー日:2021年4月13日)。 【写真】櫻井光政弁護士(弁護士ドットコム、東京都内、4月13日撮影)
最初に取り組んだのは「1審死刑」の事件
櫻井弁護士が最初に取り組んだ刑事事件は、1審で死刑が言い渡されていた身代金目的誘拐殺人事件。1982年に、自ら選んで受任した事件だ。
「当時は弁護士会館に行き、箱に入っている記録などの中から、やりたいものを選ぶシステムでした。その場にいた人たちが『死刑のものがある』と言っていたのですが、誰もその事件を取らないんですよね」
櫻井弁護士は死刑問題に関心を抱いていたものの、当時は弁護士1年目。さすがに躊躇した。しかし、いっこうに誰もその事件を取ろうとしないため、「むしろ自分がやるべきではないか」と考え始めた。
「ベテラン弁護士が忙しい中、少ない時間の中で取り組むよりも、新米弁護士が一生懸命やった方がよい結果を残すことができるのではないか。経験が足りない部分は時間や努力で補えばよいのではないか。そう思って、自分でその事件を選びました。当時の国選弁護人の力は、弁護士になりたての私からみても、不十分なものでした。ほかの弁護士が片手間でやる以上のことはできるのではないかと思ったんです」
そんな櫻井弁護士に「もし良かったら、一緒に取り組ませてもらえないか」と手を差し伸べた弁護士がいた。安田好弘弁護士(第二東京弁護士会)だ。今は「死刑弁護人」として知られる安田弁護士も、当時はまだ弁護士になって3年目の駆け出し弁護人だった。
※写真は裁判所(キャプテンフック / PIXTA)
櫻井弁護士は「安田弁護士の力量は素晴らしかった」と振り返る。裁判所と対峙する方法は安田弁護士から学んだという。
「当時の左翼の活動家たちは、勇ましいことはガンガン言う一方で、相手のこころに(自分たちの主張や思いを)届けるという意識がないようにもみえました。でも、安田弁護士は違った。普段は穏やかな人ですが、相手の懐に飛び込んで、切り込んでいく。裁判では『お言葉ですが、裁判官…こうではないでしょうか』と裁判官に向かっていくんです。
裁判官がいないところで威勢よく批判するのではなく、裁判官と直接向き合い、きちんと話をする。そのことの重要性を教えてくれました」
引き受けた後に、戦後、身代金目的誘拐殺人事件で一審死刑を言い渡された事件がひっくり返ったことはないと知った。1985年、二審で被告人に言い渡されたのは、無期刑だった。
「中の人たち」とは「対等」になれない

※写真は東京拘置所(忍 / PIXTA)
この事件を通じて、櫻井弁護士は、被疑者・被告人との関わり方についても学んだという。
当初、被告人は櫻井弁護士に「こんな自分のような極悪人の弁護を引き受けてくれてありがとうございます。先生は神様のようです」と言っていた。しかし、無期刑が確定した後、晴れやかな表情で「いやぁ、俺はこんなにひどいことをしたから、こんな若い新米の弁護士しか来てくれないんだと思ってガッカリしたんだよ。でも、よかった」と言ったという。
「『神様のようです』って言ってたじゃん!と思ったのですが、そもそも、相手と対等な信頼関係を築けると思っていた私は、弁護士として甘かったということに気づかされました。
死刑だと言われた人たちは、死刑を免れるためならば、どんなことでも言うし、どんなことでもする。(矯正施設の)中にいる人たちと外にいる人たちは違うんですよね。外にいる人は、家族などがいる場所に帰り、好きなものを好きなだけ食べられる。でも、中の人たちは明日どうなるか分からない日々を過ごしています。まして死刑判決を受けて『死んだ方がよい』と言われている人たちです。対等になれるはずがありません。
自分なりの思い入れを持って事件の対応にあたりましたが、自分の思い入れとは関係ないところで中の人たちは生きている。そのことを分からないとダメなんだということに気づかされました」
「麻雀ばかりしていた」学生時代→日々学び続ける弁護士に
ベテランの刑事弁護人として活躍する現在も「日々、学ぶことがたくさんある」と語る櫻井弁護士も、中央大学法学部の学生だった時代は勉強熱心ではなかった。
「学生時代は麻雀ばかりしていました。あとはデートしたり、旅行に行ったり。まったく勉強していませんでした」
卒業するころは学生運動の影響で大学がロックアウトされていたため、試験はすべてレポート。自分で書いたものは1つもなく、上智大学に通う優秀な友人が書いたレポートを丸写しして提出していたという。
ただ、刑事政策の基本書を読み、おもしろいと思ったことはあるそうだ。
「すこしの勉強した程度であっても、政策的な視点が入ることの重要性には気づきました。司法試験の勉強は、解釈学ばかりなので、政策的な視点が欠けがちです。政策があって、立法がある。政策的に問題がある法律ならば変えなければいけないし、法律は変えることができる。このような視点を持つことができたのは、ほんの少しですが、政策の勉強をしたからだと思います」
司法試験を受けると決意し、友人たちと勉強を始めたのは卒業後のこと。弁護士になってからも、ひたすら勉強に明け暮れる毎日だ。現在も桜丘法律事務所で、神山啓史弁護士(第二東京弁護士会)とともに勉強会を開催している。「(論語にある通り)過ちては改むるに憚ることなかれ、ですよ」と櫻井弁護士は笑う。
「正解はない」けれど…「ダメ」な刑事弁護とは?
新人弁護士の養成にも力を注ぐ。2002年から、養成の様子をつづった「桜丘だより」を「季刊刑事弁護」(現代人文社)で連載し、現在も続く。連載をまとめた「刑事弁護プラクティス」シリーズの初版は2013年に発行され、2020年12月には続編となる「刑事弁護プラクティス2」が発行された。「弁護の動き方のヒントや示唆になれば」と櫻井弁護士は語る。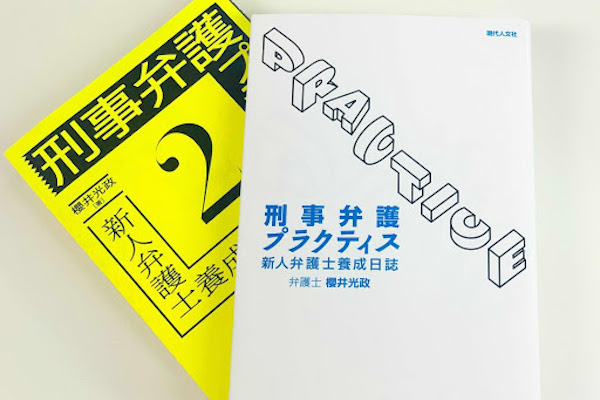
※写真は「刑事弁護プラクティス」シリーズ
ネット上には「新人弁護士は必読」など、若い弁護士に「プラクティス」シリーズを紹介する法曹関係者の投稿が複数みられる。2016年に放映されたTBS系ドラマ「99.9-刑事専門弁護士-SEASONⅠ」2話では、立花彩乃弁護士(榮倉奈々)が勉強のために同書を読んでいるシーンがあり、ドラマの中でも「刑事弁護人の必読書」とされている。
「刑事弁護の方法論に唯一の正解はないと思う」と語る櫻井弁護士。ただ、「これはダメ」という刑事弁護はあるという。接見に行かない、被疑者・被告人の話をよく聞かない、身体拘束を解くための努力をしない、現場に行って確認しない、などだ。特に、交通事故の場合、現場の確認は欠かせないという。
「たとえば、事故が起きたときに(加害者側が)標識や信号が見えなかった、枝が伸びていたと主張することがあります。ところが、事故が起きた後に現場に行ってみると、枝が切り取られていたり、ゼブラゾーン(導流帯)のペイントが変わっていたりすることがあります。(加害者側の主張を信じれば)事故当時は間違いやすくて、事故が起こりやすい交差点だったはずなのに、いつの間にかきれいなゼブラがかかっている。
もし、事故当時と、現地を確認した時で、障害物の除去やゼブラ内容の変更があったとしたら、公安委員会などが『この交差点は危ない』と認識したということが考えられます。そうなると、やはり、被疑者・被告人の過失が原因なのかということを追求するひとつの材料になるわけです。現場は『情報の宝庫』なんですよね」
刑事弁護に取り組む中で、無罪になるべき人を無罪にできなかったケースなど、やるせなさを感じることも幾度もあった。しかし、刑事弁護は「弁護士にしかできない仕事で、やりがいがある」。今日も櫻井弁護士は、若い弁護士たちとともに学び続ける。
櫻井光政弁護士プロフィール
1954年東京都生まれ。中央大学法学部卒業。1982年弁護士登録、高橋孝信法律事務所入所。1987年に独立して櫻井光政法律事務所開設、1989年櫻井・前田法律事務所開設。1998年に桜丘法律事務所を開設。「連載 桜丘だより」季刊刑事弁護(2002年~)、「刑事弁護プラクティス」シリーズ(現代人文社)など著書多数。

.jpeg)