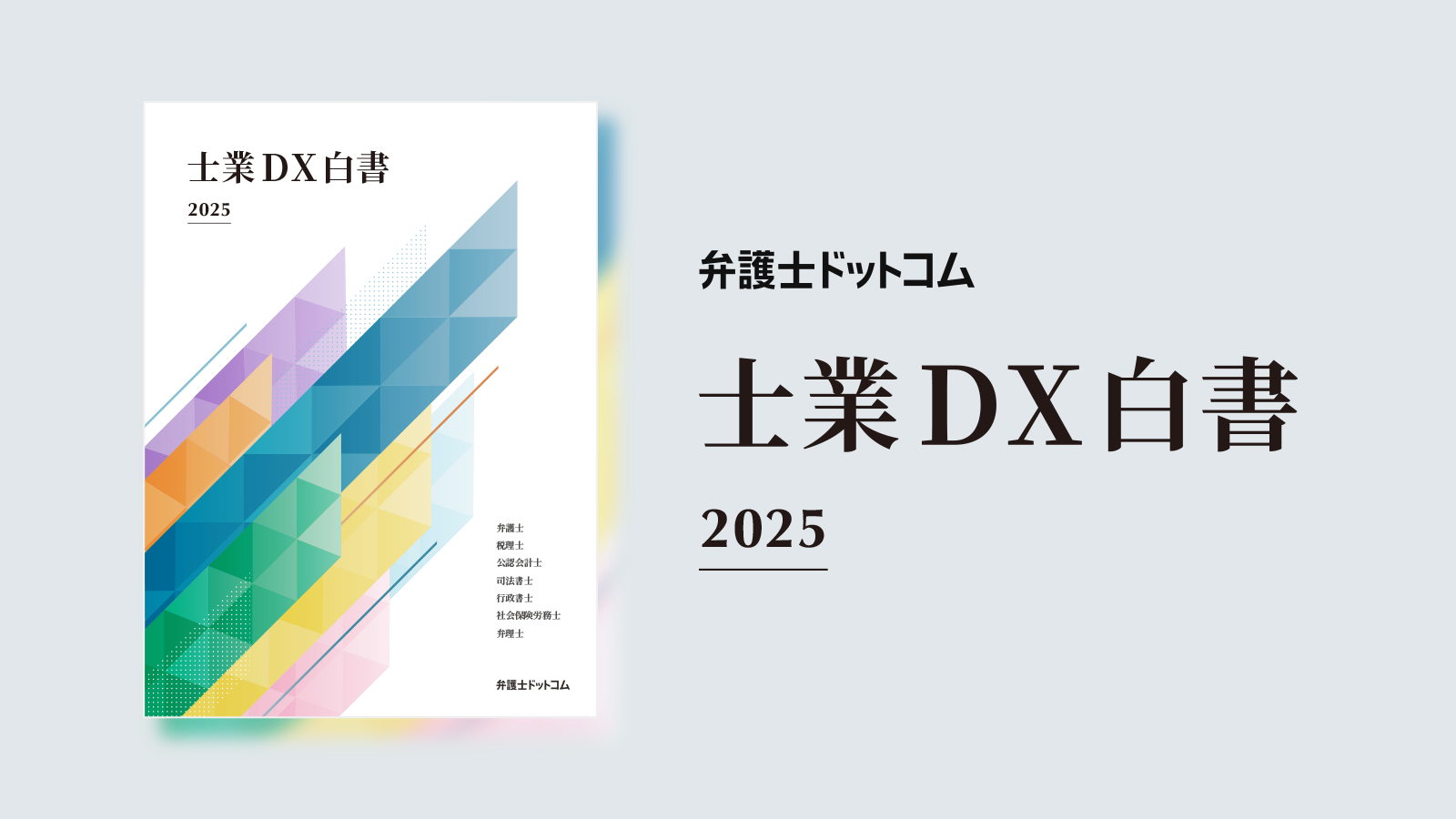「グレーゾーンの判断は士業の出番」HRbase・三田氏(社労士)が考える「AI時代の士業」
法律や会計分野におけるDXサービスは、生成AIの登場もあって、激しいスピードで進化を遂げている。この進化を担うのは、エンジニアだけではない。士業の当事者が自ら開発者として、先進的なサービスの開発に取り組んでいる。弁護士ドットコムの「士業DX白書2025」では、そんな士業当事者たちがどのような思いでサービス開発に取り組んでいるのかを聞いた。今回は、労務相談のAIサービスなどを手がける株式会社HRbaseの三田弘道・代表取締役(社会保険労務士)のインタビューを紹介する。(ライティング:国分瑠衣子)
顧問の士業がいる企業でも、AIへの相談ニーズはある
――起業の経緯を教えてください。
原体験は大学時代です。就職活動のときに周りの学生が「働くのは面倒くさい」と言うのを聞き、働くことを楽しくしたいと考えました。もともと人事の仕事に興味があったのですが、内定したスタートアップが、入社直前に労務管理事業にピボットしたんです。入社前に必死で社労士の資格を取りました。
労務は人事と同じ「人」と関わる仕事ですが、従業員の休職やハラスメント、賃金問題などトラブル対応が多い仕事です。華やかな人事の仕事とは逆ですね。ただ、企業の人事施策を成功させるには、労務管理がしっかりしていないと実現しません。
中小企業には、福利厚生を手厚くしたいと言いながら、そもそも給与体系が適当だったり、雇用契約書がなかったりというめちゃくちゃなケースが結構あります。
労務の仕事を分かりやすく、楽しいものに変えたいと2019年にHRbaseサービスの開発に着手しました。立ち上げ当初は、就業規則を作る企業向けのサービスが主軸でしたが、社労士向けに転換しました。資料を調べる業務が多い社労士にフォーカスしたほうがニーズがあったからです。
――生成AIをサービスにどう活用していますか。
2022年にChatGPTが登場し、2024年から「労務アシスタントAI(リリース時は労務相談AI)」を新機能として入れました。労務に関する質問を入力すると、AIが当社でストックしている資料から情報収集して要約します。AIが文書を生成するので、社労士は顧問先への文書作成の手間が省けます。
要約文書には、根拠にした資料も表示されるので、ソースも明確になります。最後に社労士がチェックして終わりです。AIが顧問先への回答の土台をつくるイメージです。
社労士の困りごとの一つに、調べものの大変さがあります。調べる作業は、インターネットでキーワード検索するのが一般的ですが、法律や制度の正しい名称を覚えていないと、ヒットしません。ヒットしても、国の資料は数百ページに及ぶものもあり、知りたい情報にたどり着くのに時間がかかります。この課題を解決するためにAIの開発を進めました。
ーーサービス全てにAIを活用しているのでしょうか。
AIだけでは代替しにくいものもあります。一つは情報提供系です。「労務マガジン」という、顧問先に送ることを想定したメールマガジンを配信しています。法改正などの情報をまとめた長めの記事です。
AIで短い記事もつくることはできますが、生成AIが事実と異なる回答をする「ハルシネーション」が起きる可能性もあるので、人の手で書いています。
もう一つ、AIは業務フローが長いものが苦手です。例えば、従業員が育児休業を取る場合は、年金事務所への書類提出や、福利厚生の確認など手続きがとても多い。行政の窓口も複数あります。こうした労務担当者が行う手続きを網羅したマニュアルは世の中にあまりなく、当社で開発しています。
ーー今後、事業をどう成長させますか。
社労士向けだけでなく、2024年12月からは一般企業向けにも展開しています。AIの労務担当者のようなイメージですね。例えば、例えば、今後機能開発していくのは、妊娠して育児休業を取得する社員に対する、タスク管理や、社員本人への説明もチャットボットで行えるイメージです。士業がいない会社のニーズがあると思っていたのですが、意外なことに士業がいる会社からのニーズもあります。
ーーなぜでしょうか。
顧問の士業がいても相談にはハードルがあるんです。お金をかけたくないとか、「この程度の相談をしてもいいのだろうか」という人間のプライドですね。
また、企業と社労士のマッチングも視野に入れています。社労士にしかできない価値を提供するために「AI時代の社労士塾」のようなイメージで、育成にも注力したいです。
人間同士の情緒的な側面は残る
――AIは士業の代わりを担えるようになるでしょうか。
今はAIの精度は明らかに上がっているのに、人間の感情的な理由で、AIに委ねることに追い付いていない段階です。
例えば、自動運転車が事故を起こすと騒がれるけれど、高齢者より事故を起こす確率は低くなるでしょう。AIについても、「ハルシネーション」の問題が言われていますが、専門家も間違えるので、そこまで変わらなくなってきています。それでも、「人がやっている方がいい」という感覚があります。
でも、その感覚はいつまでも続くものでしょうか。さらに技術が進化して、AIへの信頼感がどんどん高まってくれば、「人の手で行うほうが怖いことなんだ」という認識に変わっていきます。そうしたときに士業の仕事にも当然影響が出てくると思います。
さらにAIの進化として、AIが社労士の思考プロセスを学習してパターン化すれば、リアルな対話をすることができるようになります。相談者の表情や声色といったことまでわかれば、どのような潜在ニーズがあるのかをこれまで以上に汲み取ることができるからです。
あとは、人間が感情をもった生き物であることは変わらないので、人間同士の情緒的な側面は残ります。スナック的なノリですね。お酒や食べ物のおいしさという機能的な価値よりも、みんながそこにいるという情緒的な価値です。これはAIに代替できません。士業についても、感情に寄り添って、人間関係を深めるという点は残ります。
――社労士や他の士業が生き残るためには、どんなスキルが必要でしょうか。
社労士は法律を一生懸命に勉強するイメージですが、営業職のように感情に訴えることができる人は少ないので、それができると強いと思います。
セミナーで例に挙げるのが「がん告知を誰から受けたいか」ということ。心にダメージを負う辛いときに、人に寄り添って共感してもらうことが、心理的なストレスを和らげます。AIでは代替できません。謝罪も同じですよね。AIが謝っても許してもらえないことが、人だとすぐ解決する場合があります。
AIはもう何でもできるので、お金を払って人間にやらせたいことは何かを考えたほうが早い。進化のスピードも早く、40代以下の士業はどうするか本気で考える必要があります。本当に生き残れる社労士は全体の1、2割かもしれません。
ーーほかに、AI時代の社労士に求められることはありますか。
AIにできなくて、人間にできることで言えば、法律のグレーゾーンのアドバイスです。
労働基準法の「36協定」は、残業ルールを定めた協定ですが、仮に従業員100人の会社で、1人の従業員が年間のうち 1ヶ月、それも1時間だけ残業時間の上限を超えても、問題になる可能性は限りなく低いですよね。AIは倫理的な面から「残業時間の上限を超えています。下げる努力をしましょう」としか指摘できませんが、社労士であれば「大丈夫ですよ、適切な対応方法をアドバイスします」などと言えます。
労務管理を改善したいブラック企業が一気にホワイト企業に変わることなんてできません。社労士のような法律に関わる仕事は、グレーゾーンを泳ぎながらホワイトになっていくという現場が非常にたくさんあって、小さな改善の積み重ねです。
杓子定規なAIとは違い、社労士は個別の企業に応じた労務管理の提案をして、ホワイト企業にする。AI時代の社労士にいっそう求められることだと思います。
【労務相談プラットフォーム HRbase】
テクノロジーの力で企業と社労士の連携を支えて加速させ、最適な労務管理を実現するサービス。「労務相談につよい事務所をつくる」ことを掲げ、2021年に社労士向けサービスとして展開を開始した。目玉機能である労務アシスタントAIでは、AIによる関連資料の収集と要約作成、根拠資料の提示を通じて、リサーチコストを削減する。顧問先とのコミュニケーションツールとしての労務マガジンや、労務管理の業務手順・タスクをまとめた労務管理ガイド、Q&Aや書式のひな形なども提供し、労務相談をトータルでサポートする。2024年12月からは、企業の労務担当者向けのサービスの展開を始めた。
【プロフィール】
三田弘道(みた・ひろみち)
株式会社HRbase代表取締役。大阪大学大学院卒業。在学中に社労士の資格を取得し、人事労務支援を行うベンチャーに入社。2015年に株式会社Flucle(2024年11月に株式会社HRbaseに社名変更)を設立。企業の労務管理支援で感じた課題をもとに、HRbaseサービスを展開。労務相談AIの開発に取り組んだ。大阪府社労士会 デジタル化推進特別部会員。
【お知らせ】
「士業DX白書2025」では今回のような開発者インタビュー以外にも、弁護士、税理士など7士業を横断した、DX期待度スコアの算出、士業ごとの概要・課題分析、士業やそのユーザーのアンケート、DXサービスリストの作成など、多岐にわたるコンテンツを掲載しています。PDF版を無料で配布していますので、ぜひご一読ください。
詳細はこちら