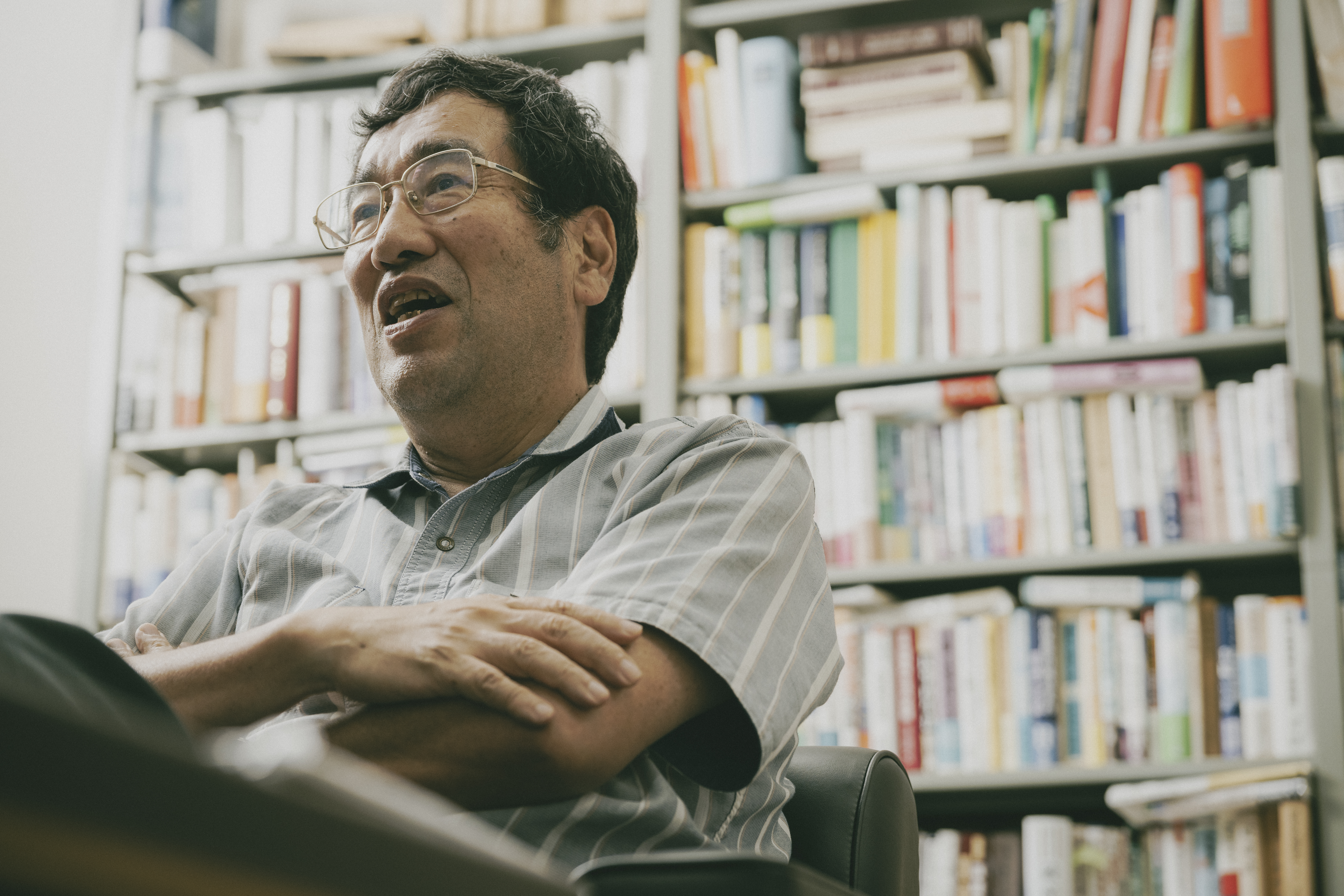AI時代の弁護士には何が必要? 民事裁判IT化を先導してきた山本和彦教授が語る「司法DX」
段階的に進む民事訴訟のIT化は、遅くとも2026年5月までに完全施行となる。その後も2028年6月までに倒産や人事訴訟、家事事件手続など、ほかの民事裁判手続が続々とIT化される予定だ。 生成AIなど、日々進歩するテクノロジーを利用して司法制度をどう変えていくべきか。「裁判手続等のIT化検討会」の座長や同検討会を引き継いだ法制審議会の部会長等として、IT化の議論をリードしてきた一橋大学の山本和彦教授に聞いた。 取材・文/園田昌也、写真/永峰拓也 (弁護士ドットコムタイムズVol.72<2024年9月発行>より)
元々は最先端だった平成の裁判システム
―遅れていると言われてきた日本の裁判制度も、ようやくIT化が進んできました
民事訴訟法が1996(平成8)年に改正された当時、電話会議システムによる争点整理や、準備書面のFAX送信などは新しい技術で、世界的に見ても画期的な部類でした。2004(平成16)年の改正では、インターネット経由の申立てを可能にする手続も作られ、実は平成の前半期は新しいテクノロジーを取り入れていく「改革の時代」だったのです。
問題は平成後半で、「停滞の時代」となってしまいました。FAXはどんどん時代遅れになっていくけれど、裁判所と弁護士は使い続けたし、ビデオ通話が普及する中、ずっと電話会議でした。平成16年改正で作ったオンライン申立ても、最高裁規則に基づくということになっていたのですが、その規則が作られないまま事実上死文化してしまいました。
停滞する日本を尻目に、諸外国は新しい技術を取り入れ、今では大きな差ができているわけです。
―オンライン申立ては、今回の民事訴訟IT化での大きな柱のひとつです。どうして条文はあったのに当時活用しなかったのでしょうか?
これは想像ですが、法律面では依然として紙がベースになっていて、オンラインで申し立てられたものを裁判所がプリントアウトして記録に綴じ込んだり、被告に送付したりという規定になっていて、使いづらかったのではないでしょうか。
他方、裁判所の仕組みとしては、新しいシステムを導入することになるので、イニシャルコストはもちろん、保守費用もかかります。その予算をどうするかとなると、日本の財政事情上、他のコストをカットしろ、ということになりますよね。裁判所の予算のほとんどは人件費なので、人減らしです。そもそも人員が十分ではないので、難しい側面があったのではないかと思います。
そういう意味で、今回のIT化で一番大きかったのは、プロジェクトが内閣官房から始まったということです。通常の検討会や法制審では基本的には少しずつ議論を積み上げていくので抜本的な改正は難しいのですが、今回は目標が先にバーンと打ち立てられた。予算面でも内閣として、要は国を挙げてやっていこうという話なので期待感があったわけです。
前回の改正ではやや不本意な結果になりましたから、検討会の座長の話がきたとき、「今度はちゃんとできるんですよね」と申し上げて、大丈夫ということだったので、お引き受けしました。
―なぜ政府は裁判IT化に力を入れようとしたのでしょうか?
世界銀行が毎年出す“Doing Business”というビジネスのしやすさランキングのようなものがあるのですが、日本の司法そのものは比較的高く評価されているのに、裁判所のIT化についてのスコアが低く、足を引っ張っていたのです。
当時の安倍晋三内閣は、日本経済の復活のカギは外国からの投資の活性化にあるという考えでした。閣議決定された「未来投資戦略2017」で裁判手続のIT化が提言され、検討会や法制審が設置されていきました。私個人としては、民事訴訟に政治が目を向けてくれることはあまりないので、千載一遇のチャンスというふうには思いましたね。
「できるところからやる」保守的な司法界の動かし方
―改正では、どのような部分を意識されましたか?
現行法でも可能な部分があったので、「とにかくできるところからやっていこう」ということです。
たとえば、争点整理手続のオンライン化は法改正前の2020年2月から実施しています。当初、裁判所側からは拒絶する弁護士も少なくないと聞いていましたが、新型コロナウイルスの流行があり、あっという間にウェブ会議が浸透しました。
新システムができるまでの間利用する「mints(民事裁判書類電子提出システム)」の運用も、死文化していた民訴法132条の10に基づき、およそ20年越しに施行規則を作って2022年4月から甲府地裁・大津地裁で試験的にスタートして、導入裁判所を増やしていきました。
2022(令和4)年の民訴法改正分についても、システムを組む必要がないものについては早い段階で施行しようということで、2024年3月から口頭弁論についてもウェブ会議化を始めています。最後の本丸は2026年5月までに実施する訴状等のオンライン提出やデジタルでの訴訟記録閲覧です。
できることから段階的に進めたのは、慣れる期間を作るという点でも良かったと思っています。IT化は始めるのは大変ですが、一旦慣れると便利で元には戻れないところがありますから。
たとえばウェブ会議も、弁護士さんは大抵裁判所の近くに事務所がありますから、そんなに使わないんじゃないのという懐疑的な意見も多かったんです。でも使い出すと、5分10分でも移動時間をなくせたほうが良いのですっかり定着しました。
―目立ちやすいのは懸念の声ですが、実際に動かしてみると杞憂であったと
私自身は利用者の利便性を高められること、とりわけ依頼者にとって自身の近くに弁護士がいるような状況を作れるのではないかというところが、IT化の利点だと考えています。
地方の弁護士さんからは、東京の弁護士が仕事を奪っていくんじゃないかと反対の声を聞くことも多かったのですが、依頼者からすれば、きちんと仕事をしてくれる弁護士であれば、自分の近くにいてほしいと思うんじゃないでしょうか。依頼者と弁護士がテレビ会議ではなく対面で話をし、弁護士が自分の事務所から裁判所にアクセスするという形を作れることが大きいのではないかと考えています。
あまり裁判所に行かなくても良いということであれば、これまでなら裁判所から非常に遠く、経営と維持が大変だったような地域にも法律事務所を置けるようにはならないでしょうか。
これまで依頼者は「遠くにある裁判所の近くにある法律事務所」まで行っていましたが、近くに弁護士がいれば、司法にアクセスするハードルが下がるのではないかと期待しています。そのためにも、IT化で裁判所に行く手間と、裁判所と弁護士との間の手間を軽減する必要があると考えています。
ただの置き換えではなく…民事訴訟DXへの道筋
―いわゆる「3つのe(e提出/e事件管理/e法廷)」は既存手続のオンライン化(デジタイゼーション)という印象ですが、新しく始まる「法定審理期間訴訟手続」は毛色が違うように感じます
「拙速な審理」などといった批判もありましたが、審理期間の長さは民事訴訟の大きな課題です。
「司法制度改革審議会」が審理期間の半減という提言をしたのは2001年のことです。当時の民事第一審訴訟事件の審理期間は平均10カ月弱でした。2000年代前半は過払い金訴訟などもあって比較的短縮が進みましたが、2010年からは逆に延びています。裁判前に解決する事件が増え、裁判所に来る事件が複雑化しているのではないかとも思いますが、現在は提言当時よりも長い10カ月超です。
私は最高裁の「裁判の迅速化に係る検証に関する検討会」の委員も務めていますが、この傾向に危機感を抱いています。審理が長期化し、いつ終わるか分からないとなれば、企業などからすれば民事訴訟は使い物にならないということになりかねないし、弱い立場の人ほど訴訟を続けられなくなるからです。特に個人は金銭面も心理的な負担も大きく、諦めてしまう人はすごく多いのではないでしょうか。審理の迅速化はむしろ弱い立場の人が裁判を受けられることを保障するために重要です。
なぜこの規定が「裁判IT化」のメニューの中にあるかというと、たとえばすでに第1回期日からウェブ会議を設定して、審理の見通しなどの方向性協議をやるとか、Teamsのチャット機能を利用して釈明や期日外でのやりとりをするとか、現場の裁判官がITを駆使して効率化に努めているんですね。IT化自体はツールでしかなく、大事なのはこれを使って利用者のための創意工夫をしていくことです。
法定審理期間訴訟もこうした取り組みの延長線上にあるもので、審理を6カ月以内に終えなくてはならないとなれば、さまざまな工夫を動員しなくてはなりません。そうした工夫やノウハウが通常の民事訴訟手続にも好影響を与えることに期待しています。
ITを活用し、ある種の無駄を省ければ、前よりも充実した審理をしながら6カ月でもやっていけるのではないかと。単にアナログをデジタルに置き換えるのではない、民事訴訟のDXとも言える仕組みです。
また、私が仲裁・調停担当執行理事を務めるJCAA(日本商事仲裁協会)では、2021年の規則改正で「迅速仲裁手続」という仕組みを設け、紛争金額が総額3億円以下の事件は仲裁廷成立から原則として6カ月以内、5千万円以下なら3カ月以内に判断が下ります。3億円というのは裁判所的には大事件ですよね。大企業同士だけでなく、一方当事者が中小企業や海外企業というケースもありますがうまくいっており、当事者の合意により期限を延長するケースもありますが、それでも7~9カ月で終わっています。
もちろん、BtoBとBtoC、CtoCとでは違いもありますが、こうした仲裁の経験からも審理期間の短縮を実現できるのではないかと感じています。
―2023(令和5)年に民事訴訟以外の民事裁判手続についても各種改正法が成立しました。民事裁判IT化で残っている課題はありますか?
令和4年と令和5年の改正で法整備は終わり、今は実際のシステムを作っている段階です。民事訴訟は2026年5月、それ以外の倒産や家事などの手続は2028年6月までに完全施行されます。
ただ実際に始まると課題も出てくると思います。私が裁判所などにお願いをしているのは、「とにかくユーザーの声を聞いてほしい」ということです。たとえば、今でも裁判所のTeamsは利用時間が限られているとか、弁護士さんから不満を聞くこともあります。裁判所に限らず、法曹界はどうしても慎重で「石橋を叩いても渡らない」ようなところがありますが、こうした態度はIT化においては致命的です。今のところ比較的よくやられていると思いますが、柔軟に改善していく取り組みが大事でしょう。
また、令和4年改正法、令和5年改正法のどちらにも附則に施行5年後の見直し規定が盛り込まれています。状況に応じて、5年と言わずすぐに改正できる体制が必要です。臨機応変に対応しないと、またすぐに古いシステムになってしまいますから。
「AI裁判官」は実現する?最新技術が裁判に与えるインパクト
―IT化の議論のときは、ここまで生成AIは発達していなかったのではないでしょうか?
制度の議論をしているときも、証拠の偽造やなりすましが起きる可能性は指摘されていました。ただ、ここまで早く現実的な恐れになるとまでは考えられていなかったと思います。見送られはしましたが、立法過程では現行法で対応できない悪用について罰則を設けるという話もあり、施行後の状況によっては5年後の見直しと言わず、早急に対応する必要が出てくるかもしれません。
―逆にAIを有効に使える部分はどこでしょうか?
一番身近なものとしては判例情報の検索でしょう。2026年に民事判決をオープンデータ化できるよう私も委員をしている法務省の「民事判決情報データベース化検討会」で現在議論しています。
オープンデータ化されれば、すべての判決情報をAIで分析できます。今はみんな一生懸命キーワードを入れて裁判例を探していると思いますが、きちんとプロンプトを入力すれば、適切な裁判例が順に出てくるようになる。そうすると法曹の業務はかなり効率化するはずです。
それから法曹の仕事のかなりの部分は「要約」が占めていて、裁判官が判決を書くときも、まずは両当事者の準備書面を要約するわけですよね。要約はAIの得意分野ですから、そういう点でも効率化を期待できるのではないでしょうか。
より長期的なところだと、判決結果の予測ですね。すべての判決を分析することで、こういう事件だったらどういう結論になりそうかという予測がかなりの精度でできるようになるでしょう。
究極の形としては「AI裁判官」があって、比較的近い将来、大まかな結論や理由を入力すると判決の原案を作ってくれる、合議体で言えば左陪席的な利用法は出てくるのではないかと思います。出力された判決文を裁判官が手直しするイメージです。
ただ、AIが結論まで考えるということになると、ある程度は可能だと思う一方で、抵抗を感じる人もいると思います。当事者に対して、AIをこういうふうに使いましたという情報を示すべきかどうかという問題も発生するのではないかと考えられます。
たとえば、イギリスでは2023年末に裁判官のAI活用についてのガイドラインが公表されました。私が聞く限り、最高裁はまだそこまでは議論していないようですが、実際にAIを使う裁判官は出てくるでしょうから、早晩議論が必要になるでしょうね。
―先ほど仲裁機関(JCAA)の話が出ましたが、裁判外の手続についてはどうでしょうか?
裁判外紛争解決手続(ADR)は、当事者が合意さえすれば、ある意味どんな手続だってできるという点で、民事訴訟法に縛られた裁判所の手続よりも自由が利きます。ITやデジタルとの親和性が高いのは確かです。ただいかんせん、利用件数が少ない。
でも、ODR(オンラインADR)は、この状況を打ち破る契機になりえると考えています。日本ではあまり馴染みがありませんが、世界最大級のオンラインマーケットプレイス「eBay」では、オンラインで完結的に紛争を解決できるようなシステムを提供しています。購入した商品の色が写真と違うとか、少し破れていたとか申し立てると、年間6000万件とも言われる過去の膨大な紛争解決結果から、AIが両当事者に対してこういう解決策が多かったと提示してくれる。ほとんどの場合はこれで解決するそうですが、双方が話し合ってもダメなときは、第三者が出てきてオンラインで調停、仲裁と進んでいく。
日本でも、裁判所やリアルのADR機関に行かなくても、スマホ1つでやり取りできて、うまくまとまらなくても第三者が現れ、みんなでオンライン会議して1~2カ月で解決するというシステムができれば、日本人の紛争解決に対する考え方が根本的に変わる可能性があるんじゃないかと考えています。そのためにもAIが実力を発揮できるよう、判決だけでなく、和解やADR/ODRの紛争解決情報についてもビッグデータを形成していく努力が必要です。
そして、ODRの発展が裁判にも良い影響を与えてくれることを期待しています。裁判というのは公共サービスですから基本的に競争相手がいません。ただ、みんなが「ODRいいね」となって裁判が使われなくなったら、たまたま裁判を利用した人の「なんで次の期日は1カ月後なんですか」といった疑問を無視できなくなりますよね。ADRは裁判と似たようなスキームなのであまり競争になりませんが、ODRで根本的な発想が違うものが出てくると影響が大きいんじゃないかと思っています。
AI時代の法曹には「想像力と創造力」が必要
―今後AIの登場によって、法曹の仕事はどのように変わると思いますか?
AIをはじめとした技術を使いこなせることが大前提になるでしょう。ただ、インターフェイスももっと親切になるはずで、使いこなすための特殊技術は少なくなっていくのではないでしょうか。そういう意味でも、かなりの部分はAIに代替されそうです。
すでに検索や要約機能は人間を凌駕していますので、若手がやっている判例情報の検索、文献を要約してボスに伝えるといった仕事はなくなるかもしれません。特に若手にとっては大変な時代です。
そうした中でどうやって付加価値を見出していくか。私は「想像力と創造力」だと思っています。AIは過去に規定される。少なくとも新しいことを考えるのは苦手です。法律家として、いかに新しいものを作り出すかが重要になってきます。
弁護士の基本的な仕事は、依頼者の状況に思いをいたし、最善の解決策を見つけだすことです。一方、AIは一般化した情報に基づいて、一般化した回答を出す。どこまでいっても一般化した解です。具体的な個々の事件をみて、想像して、もっとも適当な解決を探るのは引き続き人間の仕事になります。
あるいは類似の判断がないような状況で新しい判断をしていく。最近の最高裁判例だと、性別変更後の女性を父と認定したものがありました。「女性であっても父親」というのは誰も考えてこなかった問題です。こうしたクリエイティブな活動は人間にしかできないでしょう。
ただ、そのためには裁判官がもっと余裕を持つ必要があります。事件処理に追われて、本も読めないようでは想像力/創造力を発揮できません。AIでできるところはAIに任せて、人間にしかできない主体的判断に力を割けるようにする必要があります。
―山本先生は一橋大の法科大学院長(2019年4月~2021年3月)でした。AI時代の法曹養成をどのように考えていますか?
一橋ローでは、司法試験はあくまで通過点で、法曹になったあと通用する能力を養成するという理念でやっています。学生から見ると遠回りのように見えるかもしれませんが、それこそが近道なんだと。高い合格率が、その方針が決して間違っていないことを示していると思います。
「自助・公助・共助」と言っていますが、勉強は自分、公助は先生、そして学生同士が勉強会を作って切磋琢磨する。想像力/創造力を自習で身に付けるのは困難で、先生や学友と議論する中で培われていく能力だと考えています。
その意味で、予備試験は自助の世界に近いものだと思います。もちろん予備出身でも立派な人はたくさんいますが、知識的なものは今後AIで代替できてしまう中、想像力/創造力を養う機会を多く提供できる「フォーラム」という点で、ロースクールの重要性は増していくと信じています。
また、想像力/創造力という点では、より多様な視点が必要です。学部を3年で卒業する「3+2」の法曹コースもできましたが、そうした学生ばかりではロースクールの力を十分発揮できません。幸いにして、一橋では他学部や社会人出身者が再び増えつつあります。異なるバックグラウンドを持っていることは本人の強みになりますし、多様性ある法曹界は社会にとっても望ましいことです。
私個人としては、弁護士は「社会の医者」だと思っていて、全国津々浦々にいてほしい存在です。今後も弁護士の数は増えていくでしょうし、多様な弁護士を育てられる一橋でありたいと思っています。
法定審理期間訴訟手続
令和4年成立の改正民事訴訟法で新設された訴訟手続。最初の期日から5カ月以内に争点整理を終え、6カ月以内に弁論を終結し、7カ月以内に判決を言い渡すというもの。審理期間を予測可能・迅速化することで訴訟の利用を促進するねらいがある。
一方で、成立過程では当事者の手続権を害する恐れや拙速な判断がなされる可能性も指摘され、各地の弁護士会などから懸念の声もあがった。
懸念への手当として、申立てに当たって当事者間に同意があることや、当事者はいつでも通常の手続に移行できること、判決に不服がある場合は控訴とせず同じ審級で通常審理をやり直すことなどの規定が設けられている。また、十分な訴訟対応能力のない当事者に不利になることから消費者契約や個別労働関係民事紛争など、当事者間に力の差がある類型は対象外とされる。
なお、海外ではフランスに当事者間で期間を合意して審理を進める手続があり、イギリスにも迅速審理の手続類型「ファスト・トラック」等がある。
山本 和彦(やまもと かずひこ)氏
1961年兵庫県生まれの法学者。84年に東京大学法学部を卒業し、同年から同大助手。東北大学法学部助教授を経て、現在は一橋大学大学院法学研究科教授。専門は民事手続法。本インタビューに関連した著書に『民事裁判手続のIT化』(弘文堂、2023年)、『ADR仲裁法[第2版]』(日本評論社、2015年)などがある。民事裁判IT化では、「裁判手続等のIT化検討会」や「民事裁判手続等IT化研究会」の座長、法制審議会の民事訴訟法(IT化関係)部会部会長、民事判決情報データベース化検討会座長などを務める。第一東京弁護士会登録。