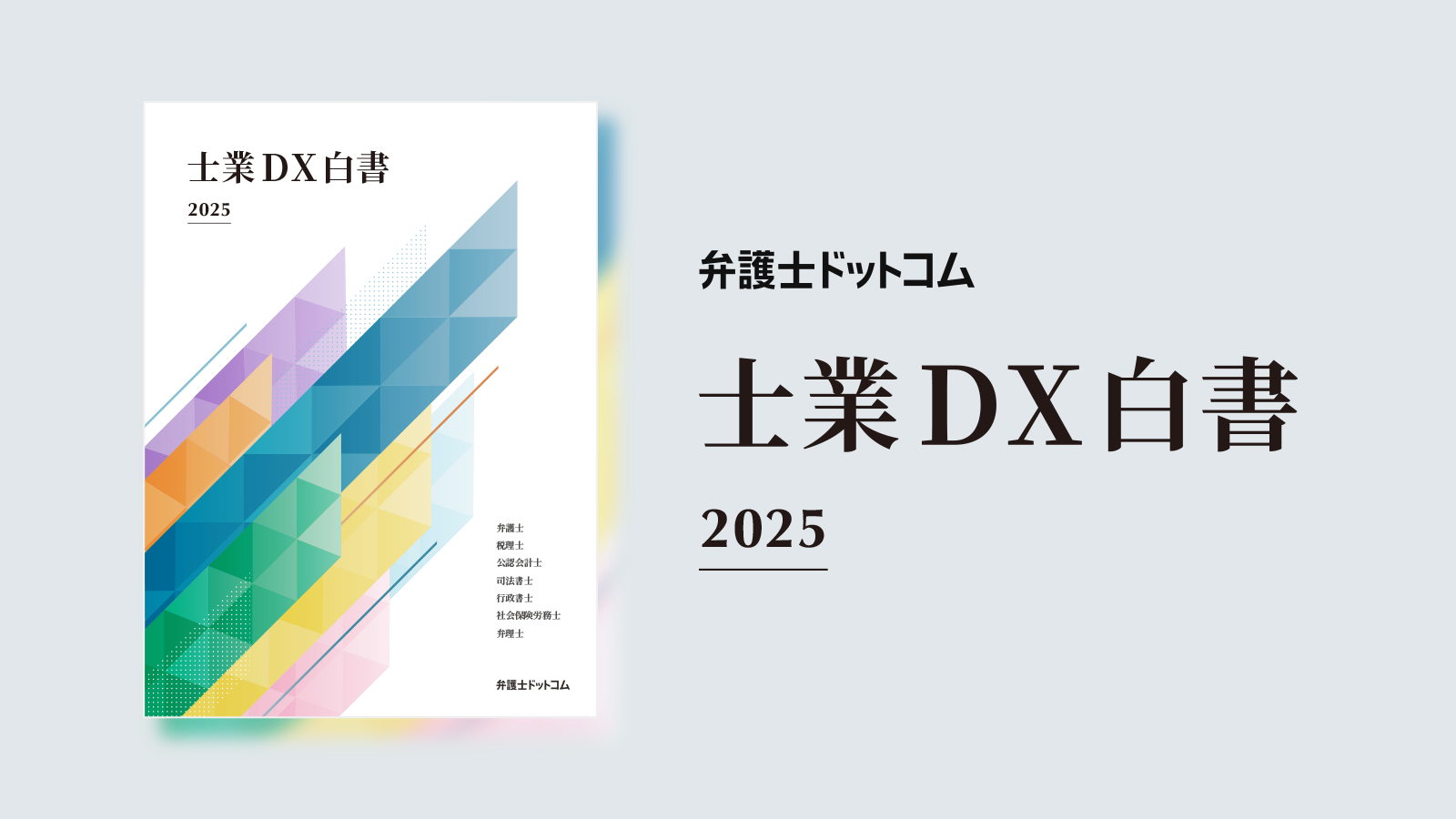【弁護士DX座談会】AI時代の法律事務所はバイネームで依頼される「スナック」を目指せ
生成AIの出現により、さまざまな業界でDX(デジタル・トランスフォーメーション)が加速している。士業も例外ではなく、従来の業務形態が大きく変わろうとしている。法曹業界を例にとっても、契約書の作成やリーガルチェック、判例検索の効率化にとどまらず、法的判断の補助や顧客とのコミュニケーションにまで、AIの活用領域は確実に広がりを見せている。 こうした変革期にあって、士業に求められる役割は何か。リーガルテック企業「GVATECH」代表の山本俊弁護士(写真左)、キャンセル料回収サービス「ノーキャンドットコム」を運営し、士業の経営支援にも注力する北周士弁護士(写真中)、使用者側弁護士として人事労務分野のテクノロジー活用に通じ、企業人事のコミュニティ作りにも取り組む倉重公太朗弁護士(写真右)の三氏が集まり、生成AI時代の法曹の未来について議論した。司会は新志有裕(弁護士ドットコム・プロフェッショナルテック総研部長)。(座談会は2024年10月4日に開催) (士業DX白書2025、弁護士ドットコムタイムズVol.74<2025年3月発行>より)
業務プロセスを蓄積して、ナレッジとして活用
司会:早速ですが、弁護士業務のデジタル化は進んでいると思いますか。
山本:一定以上の規模があれば、何かしらデジタル化に取り組んでいる事務所は増えてきたと思います。デジタル化すると、業務プロセスが集客から法律相談を経て案件を進めて終了のところまで、全てがデータとしてたまっていきます。そして、そのデータを再活用できます。
これまでの法律相談の内容をすべてデジタルデータとして残して、同じ事務所で活用できたら、ナレッジの共有として結構意味があるものになります。
倉重:他の事務所でもそれぐらいやってるところはあると思いますね。相談内容を全部データ化していくってことですよね。
山本:企業の人事の方もDXを進めていますが、人事の方々が目指すDXは何のためにやってるように見えますか。
倉重:HRテック(HumanResourcesTechnology)と言われる分野ですね。最近では、人事部門の業務をAIなどの技術を使って効率化するサービスを提供する企業も出てきています。
弁護士のDX、未だ「効率化」の段階
倉重:そもそも、デジタル化には4つの段階があります。
最初は、紙で管理していたものをデータ化する段階。二つ目が、業務効率を高める段階です。次に、業務の自動化です。契約書のチェックとか、弁護士であれば誰でもできることを自動化していくプロセスです。最後に、高付加価値化という段階にいたるわけですが、これらの動きが人事業界でも始まりつつあります。高付加価値化という点では、「こういう施策をやった方がいいよ」とか、「この人にはこうアプローチした方がいいよ」といったことを生成AIが教えてくれるというところまではいくと思います。弁護士業務でいうと、「相手方がこうした主張をしてきた場合は、こう反論した方がいいよ」ということですかね。
北:そこまで実現するには、まだかなり距離がありそうですね。紙で保管していて、個々の弁護士の頭の中とファイルの中にしかなかったデータがまずデジタル化され、共有される。共有することで効率化が図れる。過去のデータが読みやすくなったり、職場の中で共有がしやすくなったということはあるかもしれません。
倉重:人事業務においてテクノロジーをどう使うかについては、企業の認識にはまだまだ温度差がある印象です。例えば、人事評価に利用して、従業員の賃金の変動とAIによる評価とが直結するという話になってくると、そもそもその根拠は正しいのかということも問題になります。弁護士業界でいえば、「AIを活用して裁判の主張を組み立てます」という弁護士がいたとすると、その主張が正しいものであったとしても、「そんな弁護士で大丈夫か」と考える人は多いでしょう。そういう意味では、弁護士業界はまだ高効率化の段階で止まってるかなという印象です。
山本:効率化段階(2段階目)で、まだ自動化(3段階目)には至っていないという認識ですね。せいぜいAI契約レビューツールで契約書の危ないところをチェックしますよというぐらい。リーガルテック全般で見ても、判例検索システムがちょっとくらいですかね。パラリーガル的な作業や調査はある程度できるかもしれませんが。
AIは専門性が高い分野ほどなじみやすい
司会:9年前のデータですが、野村総研と英国オックスフォード大学の研究によると、税理士の業務の92.5%がAIに代替されるのに対して、弁護士業務の代替可能性は1.4%にとどまりました。これからAIに代替されていく弁護士業務はどれぐらいあると思いますか。
山本:その1.4%は、おそらく裁判業務を念頭に置いていると思うんですよ。
僕も以前はAIが法曹の業務をやるのは絶対無理だと思っていましたけど、生成AIの登場で考えが変わりました。というのは、専門性が高ければ高いほど、厳格なルールがあるのでAIになじみやすいんですよ。一定のルールで進行する裁判と親和性は高いと思います。
司会:イメージ的にあとどのくらい技術が進歩すれば実現すると思いますか。
山本:今の技術でもいけると思います。もちろんデータとのバランスの問題があるんですけれど、データをうまく整理して入れ込んで、研究がうまくいけば、僕は結構いけるんじゃないのかなと思う。
倉重:これまでは、いわゆる定型訴訟みたいな裁判だけが代替されるイメージだったと思います。知財とか、労働事件とか。
山本:ちゃんとデータさえ揃えば、ということです。たとえば倉重先生の労務相談とかを全部記録して、AIで学習させればいいんじゃないかな。
司会:「倉重bot」みたいなのができるのでしょうか。
山本:その領域のプロフェッショナルを超えるのは難しいけど、平均的なラインは超えてくるのではないでしょうか。
どれだけAIが進化しても、最後の判断は人間であるべき
北:「感情を扱うのはAIよりも人間の方が得意」と言われていますよね。AIは込み入ったコミュニケーションや、相談を受けることは苦手だということですね。
でも実は、私自身、込み入ったコミュニケーションがあまり得意じゃないんですよ。それをChatGPTに「こんなメール来たんですけどこれってどううまく返せばいいですか」って聞くと、私なんかよりもいい回答というか、ちょっと人格者っぽい回答を出してくるんですよ。だから、意外とAIはコミュニケーションもいけるんじゃないのかなと思っています。
倉重:従業員が業務報告するとAIがフィードバックしてくれるといったツールを導入している企業もあります。下手な上司より今後の改善点とかをうまく提案してくれたり、褒めたりしてくれるんですよ。
北:おそらく正しいデータさえ学習させれば、色んな領域で平均以上のアウトプットをしてくれるというのは共通認識だと思います。コミュニケーションでも、おそらく苦手な人よりはできるでしょう。それに加えて、AIは疲弊しないので、無限に相手に寄り添えます。
感情的なクッションとして受け止めてくれるという点で、むしろ人間より我慢強いですよね。ただ、最後の価値判断をAIに委ねるところまではいっていないと思うので、価値判断をするのは、あくまで人間だと思います。それと、今のAIは質問してこない。「こういった情報はありませんか?」といった感じで、欠けているピースを聞いてきたり、「嘘をついていませんか?」と疑ってきたり、といったところまではいっていない気がしています。
山本:ChatGPTとかの進化がすごくて、現状でもいろいろできるなと思ってたんですよ。
北先生がおっしゃったヒアリングみたいなことも、試したことはないけど、結構やれるのかなと思ってます。例えば離婚訴訟で、どこまで証拠を集めれば立証に足りているのかをデータとして入れておけば、「これが足りてない」「もうちょっとこういう話はないですか?」とか、聞いてくることが可能になる。
倉重:ChatGPTを弁護士向けにカスタマイズするとしたら、どんなものができそうですか。
山本:イメージしているのは、訴訟類型ごとに一定のデータを学習させた上で、ヒアリング用のテンプレートを作る。すると、AIが顧客に対して、「この項目を埋めてください」「この証拠はありますか?」みたいな感じで整理していってくれるようなものですね。大規模事務所では、すでにパラリーガルがやっていることです。
北:膨大なLINEの履歴とかのデータを入れて、「不貞行為の証拠になりそうなものをピックアップしてください」というのもありそう。
倉重:人事労務の領域では、採用面接などの選考過程でのAI利用が一番多いんですよね。
24時間いつでも受けられるから、採用側と日程調整しなくて良いので学生にもメリットがあるし、人事側もコストを削減できます。
北:AIは、判例変更を引き出すような画期的な書面を書けるかどうかは微妙だと思いますが、パラリーガルの方やアソシエイト1年目の弁護士などがやっている業務の代替になりうるかもしれません。そうなった時に、弁護士がやらなければならないものって何ですかね。
倉重:やっぱり、最後の部分は、人が伝えないと納得感が生まれないんじゃないですか。離婚とか相続とか和解とかもそうですけど、人の人格とか感情に結びつく場合、途中までAIの力を借りたとしても、最後は人間が取捨選択して主張する部分に意味があるんだろうなと思います。
司会:そういう意味では、弁護士業務のうち、代理人という部分はAIはどこまで代替できるのでしょうか。
山本:日本って高齢化社会じゃないですか。そこは結構影響するんじゃないかと思います。おそらく、高齢者はAIの言うことに説得されるイメージがないと思います。
ただ、AIネイティブ世代が出てきたときに、その世代は、AIと人の垣根なく受け入れる可能性もあると思うんですよ。高齢化社会である日本は当分の間、人が人を説得しない限りは動かせない社会のままなんだろうなという気はしています。AIが客観的に正しい判断をしても、それを伝えて人を動かすのは難しいと思います。
北:確かに正しい答えはAIの方が出せるようになってくる。ただ、正しければ人が納得するのかというとそうでもない。
AIが、なぜ正しいと判断したかを説明をするのは結構難しいと思うんですね。
今のAIって途中の過程がブラックボックスになっていて、なぜそう判断したのかあまり説明するようになっていないと思うんですよね。
山本:でも、最近ではどのデータから判断したかとか言ってくるんですよ。
ChatGPTにいろいろ聞いて、例えば二つの選択肢から何か結論を出してきたときに、「もう一つの選択肢と悩んだりしてませんか」と聞くと、「実はこういう点で悩んだ」みたいなこと言ってきたりするんですよ。
そう考えると、弁護士よりも裁判官の業務の方がAIに馴染むんじゃないかとも思うんです。主張・立証を揃えて、過去の判例に従って判断するというのは、AIに馴染むようにも思える。
倉重:一審の前段階でAIが判断するという予備審のような仕組みはあってもいいんじゃないかと思います。企業の採用でも、エントリーシートのAIによる予備審査は既に多くの企業で行われています。
AI集客の可能性、予防的な業務や問題の早期発見に期待
司会:北先生に伺いたいのですが、弁護士は、人とのつながりの中で仕事がまわってくるという側面があると思います。集客という部分をAIで自動化できる可能性はあると思いますか?
北:AI集客に向いている分野とそうでない分野があると思います。今思いついたことですが、例えばLINEに何らかのアプリを入れると、LINE上で交わされる会話の内容をすべて読み込んでくれて、「夫婦げんかをした」「親が亡くなりそう」といった会話をすると、スマホに「離婚や相続の相談は〇〇法律事務所へ」などと問い合わせの導線を表示する−−。
そういったことは可能ではないでしょうか。
弁護士の集客で難しいのは、予防的な業務や問題の早期発見です。それがAIで可能になるのではないかという点を期待しています。
法的紛争の芽をAIがいち早く発見して、「あなたはいますぐ弁護士に相談した方がいいですよ」と忠告する。
先ほど、倉重先生が人事労務の領域では既にAIとの面接が行われているという話をされていましたが、それと同様に法律事務所に電話するとAIが24時間体制で初期対応に応じ、翌日の朝には、弁護士がAIからまとまった状態で情報を受け取る。そんな未来はあると思うし、「街弁」の生き残り策があるかも知れない。
作業的な仕事はAIで代替、生身の弁護士は個性を押し出そう
司会:AIは事務所経営のあり方にも大きな影響を及ぼしそうですが、小規模法律事務所の生き残り策という点では、どのようなことが考えられますか。
北:小規模事務所って、弁護士にとってはすごくいいシステムだと思ってるんですね。自由度も高いし負担も低いし。ただ、それが顧客のメリットに結びついているのかは考えないといけない。メリットになりうるとしたら、一つは価格の柔軟性です。小さい事務所はコストが低い。もう一つは、バイネームで依頼できることです。倉重先生に頼みたいなら、倉重先生にお願いできる点。大きな事務所は担当が細かく分かれているのでなかなか難しい。
倉重:クオリティやコストの話は確かに重要だと思うんですけど、北先生のお客さんの中には、北先生じゃなかったら怒る人っていますよね。スナックの常連客は、そのスナックのママに会いたくてスナックに通うわけですよね。それと同じで、弁護士にも「スナック北」というか、そういう要素があるわけじゃないですか。
北:そういうスナック戦略がこの時代とても大事なんじゃないかなと思ってます。生き残っていくためにという意味で。ファンを作って、ファンと一緒に高まっていく、といいますか。
作業的な仕事をAIがある程度代替してくれるので、生身の弁護士は個性を押し出していく必要があると思うんです。
倉重:今まで弁護士の数がそもそも少なかったりして、そういった努力をしなくても何とかなってきちゃったものが、いよいよきつくなってきたという現状じゃないですか。
周りが弁護士ではない環境をつくることが大事
司会:定型業務がAIに代替される可能性が高まっていく中で、士業はコンサルに活路を見出せということが散々言われていますが、弁護士がコンサルティングをする場合、何が重要になりますか。
倉重:訴訟になるケース自体が減っています。そういう中でコンサル的なことをやっている弁護士って、例えば人事の分野で言うと、紛争になる前の前の前の前から関わっているんですね。例えば人事の定例会議に出席して、そこで新しい制度のアイデア出しの段階から参画するとかですね。あくまで法律をベースにしたコンサルですけど。あとは、新しい制度を始めたときに従業員の反応をみたり、最初に文句を言ってきた従業員への対応であったりとか。
これは人事労務の分野でのコンサルですが、事業への理解度が高ければ経営コンサル自体にも対応できるのではないかと考えています。
山本:私もやればできるんじゃないのかなって気がするんですよ。弁護士が特定の分野に数多く対応していると、いろんなパターンが頭に入ってくるので、その辺のコンサルよりできるレベルまでいっている可能性もあると思う。
倉重:法律と関係ないところの話をどんどん聞きにいかなければならないのに、それをやっている人は少ない。僕も、労働法だけでなく、経営学や経済学、組織論、キャリアデザイン論なども勉強しています。法律だけ勉強していたらコンサルなんてできるわけない。
北:隣接分野を含めてそこに興味を持ってできるかどうかですよね。
倉重:好きじゃないと無理ですよ。それに、弁護士同士で割と固まりがちな人も多いじゃないですか。
特に若手は、周りが弁護士ではない環境をつくることは大事だと強調したいです。
司会:弁護士は紛争解決するものだっていうイメージを、顧客も弁護士自身も持っているんでしょうか。
倉重:紛争解決を通じていろんな事例を知ってるからこそコンサルもできるという面があると思っています。紛争処理だけが弁護士の仕事ではないというイメージを、もっと我々自身が持つべきでしょう。コンサル的な仕事は、おそらくDXがどれだけ進歩しても需要として残ると思います。
山本:僕も弁護士1年目、2年目のときは、何か専門性を持とうと考えたりしてたんですよ。細かいことは忘れたけど、10個くらい候補がありました。
その中で覚えているのが、一つは海事代理士です。船舶登記や船舶登録、船員に関する労務など海事に関する行政機関への申請などの手続きを代行する人で「海の司法書士」「海の行政書士」とも言われる人たちです。そういう人たちの集まりによく行ってました。その関係で日本マリン倶楽部という海や船をテーマにして活動しているNPO法人に入会しました。
もう一つは一次産業です。事業継承の問題とかがあって、面白そうだと思って、農業関係の人たち向けのセミナーにも参加したりしてました。そこで耕作放棄地の問題を知ったりしたんですよ。多分無限にあると思うんですよね、そういうのって、そういうところに行って、そこの人たちと仲良くなって、法的課題を見つければ専門性はいくらでも増えそうな気がします。地方でも町おこしとかやってるじゃないですか。
倉重:町おこしをやってる所って地元のいろんな人が集まってやってますよね。そこでやっているイベントとか、新たに商品を生み出すことなどを考えていくと、絶対法律問題が出てくるんです。そこに弁護士の活躍の場ってあると思うんですよ。
北:待ってるんじゃなくて、探しに行くってことですね。AIにできないことは何かっていうと物理的に人と会いに行くことなので、物理的に人と会うことを意識的にした方がいいと思っています。
単なるショートメッセージの自動送信をDXという現状は、かなりやばい
司会:今後、弁護士業界全体として取り組むべき課題は何でしょうか
北:結局、クライアントの利益をどうやって実現していくのかということでしょうか。権利があるのにそのことを認識していなかった人や、実現に手間がかかりすぎるので権利を放置してきた人がたくさんいます。AI活用やDXで弁護士の生産性や接触可能性が上がれば、いろいろできるんじゃないかと思います。
私が立ち上げた飲食店や美容室向けキャンセル料回収代行サービス「ノーキャンドットコム」が、DXの文脈で語られている弁護士業界の現状って、率直にかなりやばいと思うんです。やっていることは単なるショートメッセージの自動送信システムです。逆に言えば、それさえやっている弁護士がいなかった。
山本:権利実現ができてない分野がいっぱいあるわけですよ。それを何らかの工夫によって、解決していくのはすごくやっていきたいです。弁護士の数にも限りがありますし、弁護士全体の所得を上げつつ権利実現を社会全体に行き渡らせるためには、テクノロジーが必要だと思うんですよ。
北:弁護士が1つ3000円の案件を人力でやればコストに見合わないわけで、「ノーキャンドットコム」は、これをシステムで自動送信するという仕組みです。先端的な技術は何も使っていない。それでも、これまで数年間で3万件の依頼をいただいているわけです。もともとが紙とFAXの業界なので、枯れた技術でいいんですよ。
倉重:話は変わりますけど、最近労働組合ってすごく衰退しています。なぜかと言うと、会社員1人1人のキャリアの価値観が変わってきて、終身雇用でもないからです。そういう時代に、会社の中でどうステップアップしていくかを考えると、個人エージェントみたいな制度ができないかと考えています。でも、弁護士が労働者個人のエージェントとして付いて年俸交渉をするのは、プロ野球選手のように年俸が高くなければ難しい。でも、AIを使ってある程度自動化して、最後は弁護士が対応しますといった仕組みができれば、可能性はあると思ってます。
議論はいいから早くやろうよ
司会:最後に、自身が今後、DXとどう向き合っていきたいのかを教えてください。
山本:法とすべての活動の垣根をなくしたいということですね。日本は法治国家なので法が適用されない地域ってないわけですよ。なのに、法とそれらの活動の結びつきが弱い部分がある。これをテクノロジーを使って解決するために、弁護士にツールを提供して、その垣根を埋めてもらえればと考えています。
倉重:朗らかに働く人を増やしたい、いい気持ちで働く人を増やしたいと思ってこれまでやってきました。それも今までなかった弁護士の関わり方だと思います。紛争解決だけじゃなくて、より良い働き先の提案というところまで、弁護士が一緒にやっていくという未来は可能だと思っています。
北:「権利の実現を容易に」するっていうのは5年ぐらい前からやっていて、これからも続けていきます。抽象的に権利があるといっても実現しなければ意味がないですからね。
山本:北先生はいろんなアイデアをたくさん持っているし、実際に形にできてるわけじゃない。
でも、自分でやることにこだわってないんですよ。だから僕は北先生には弁護士コンサルのような形でいろんな人の事業の立ち上げをサポートしていくみたいなことをやって、ぜひ業界を盛り上げてほしいなと思ってるんですよ。
北:でもね。アイデアを出しても誰もやらないんですよ。「議論はいいから早くやれよ」って思ってます(笑)
【プロフィール】
▼倉重公太朗(くらしげ・こうたろう)弁護士
第一東京弁護士会。58期。KKM法律事務所代表弁護士。労働問題の使用者側の弁護士として、労使問題などに取り組む一方で、企業内セミナー、人事労務担当者・社会保険労務士向けセミナーなどを多数開催している。人材マネジメントの専門団体であるNPO法人日本人材マネジメント協会(JSHRM)副理事長。経営法曹会議・日本労働法学会・日本産業保健法学会・日本労務学会・キャリアデザイン学会会員。
▼北周士(きた・かねひと)弁護士
東京弁護士会。旧60期。法律事務所アルシエン。飲食店や美容院、ホテルの無断キャンセル問題に対処するため、携帯電話のショートメッセージを活用したキャンセル料回収代理サービス「ノーキャンドットコム」を立ち上げる。2019年12月から約5年で依頼件数は約3万3000件以上、請求依頼額は3.5億円を超える。事務所経営のセミナーなど、士業支援にも積極的に取り組む。
▼山本俊(やまもと・しゅん)弁護士
第二東京弁護士会。62期。弁護士法人GVA法律事務所代表弁護士。鳥飼総合法律事務所を経て、2012年にGVA法律事務所を設立。スタートアップ向けの法律事務所として、創業時のマネーフォワードやアカツキなどをサポート。2017年1月にGVA TECH株式会社を創業して、代表取締役に就任。リーガルテックサービス「OLGA」「GVA法人登記」などを提供している。
【お知らせ】
この座談会を収録している「士業DX白書2025」では、弁護士、税理士など7士業を横断した、DX期待度スコアの算出、士業ごとの概要・課題分析、士業やそのユーザーのアンケート、サービス開発者インタビュー、DXサービスリストの作成など、多岐にわたるコンテンツを掲載しています。PDF版を無料で配布していますので、ぜひご一読ください。
詳細はこちら