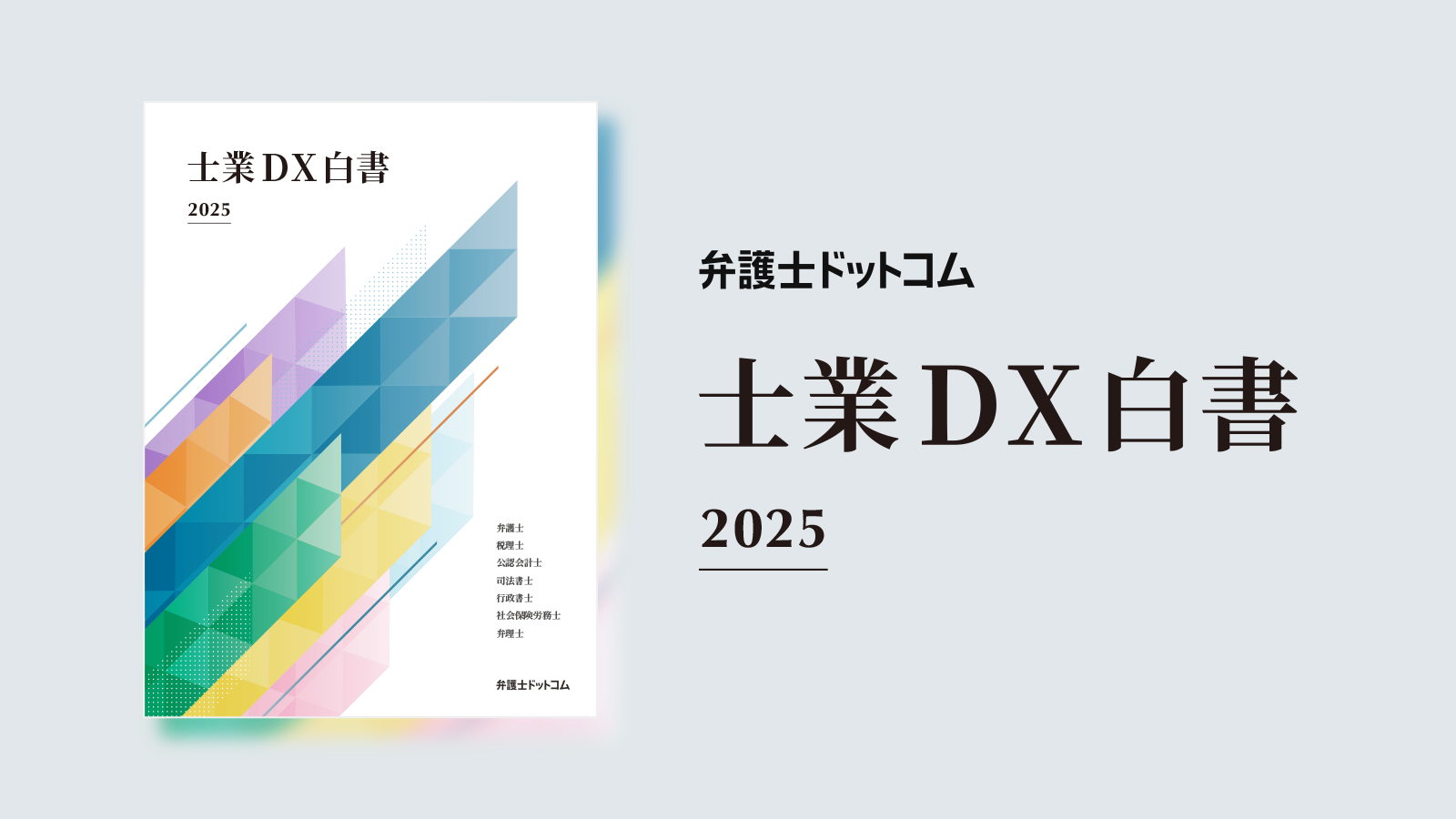AI時代の士業、本音トーク「レアな存在になれ」「なんで導入が遅れてる?」
生成AIの急速な進化が起きる中、弁護士を含む士業はAI時代をどう生き抜くべきか。弁護士ドットコムでは、「7士業」のAI活用やDXの見通しなどについて調査・分析した「士業DX白書2025」を2025年3月に発刊し、記念イベント「士業DX時代のキャリア戦略」を開催した(3月26日)。 登壇したのは、ベンチャー・スタートアップ支援をメイン領域として、複数の士業が所属する事務所を経営する菅原稔氏(弁護士・AZXProfessionalsGroupマネージングパートナーCOO)、税理士業界のDXをリードする朝倉歩氏(税理士・サン共同税理士法人CEO)、労務相談AIなど、生成AIを使ったサービスを展開する三田弘道氏(社会保険労務士・株式会社HRbase代表取締役)。司会は、士業コンサルタントの横須賀輝尚氏(特定行政書士)。AI時代の士業のキャリア形成や、今後狙いどころになる分野について縦横無尽に語り尽くした。(写真:左から横須賀氏、朝倉氏、菅原氏、三田氏) (企画:新志有裕、ライティング:国分瑠衣子)
生成AIの成長は“指数関数的”「3年目のアソシエイトレベル」
横須賀:生成AIが登場したここ数年でどんな変化がありますか。
菅原:弁護士業界はリーガルテックのプレーヤーが爆発的に増えました。でも、2年前ぐらいに契約書レビューを使ったときは、全く使えませんでした。一般の事業会社ならいいかもしれないけれど、弁護士事務所で言えば、1年目のアソシエイトと変わらないレベルで、2年目まではいけないという感覚でした。ただ、ここ半年ぐらいAIリサーチ系のツールを使うと、3年目のアソシエイトレベルのものを出してくるんですよ。そこそこ文献を引いてくるし、一つ一つの文脈を分かった上で聞いてくるんです。だから『あのツールを使ってみたけど全然だめだった』という感覚を持っている方は、もう1回触ってほしいです。
三田:一番大きいのは、生成AIの進化が指数関数的ということです。ChatGPTが出てきて1年ぐらいと、ここ1カ月ぐらいで進化の幅が同じぐらいです。当初、SNSではChatGPTについて反応する“驚き屋さん”がたくさんいた印象でしたが、最近は驚き疲れて何も言わなくなってしまった(笑)。
AI活用の広がり鈍い「いまだに紙」「デジタル化の経験値が不足」
横須賀:みなさんの業界でAI活用は進んでいますか。
菅原:まだまだですね。AIができることが増えるにつれ、大手弁護士事務所が開発費を投じてきました。でも、ここ半年間のChatGPTの成長が著しいので、各事務所が独自に開発したツールは、それほどいかされていないんじゃないかなと。
三田:社労士業界は、電子申請にすらなっていません。e-GovがAPI連携できた時点で、外部からe-Govにデータを自動送信できるようになりました。でも、いまだに紙発行、郵送、窓口の世界です。地方に行くと、窓口で知り合いに会ってお茶を飲むのがいいという人もいます。ただ、20代の若手たちはペーパーレスでAI活用が多いですね。若手のほうが将来への危機感があります。
朝倉:税理士もAI活用の成功事例が少ないですね。クラウド会計2.0が出ていいのは分かっているけれども使いこなせない。採用が厳しい上に、税理士事務所の平均人数も4〜5人の業界です。事務所が約3万あって税理士は約8万人いるけれども、法人化しているのは5000法人ほど。ほとんどが個人事業所で、人繰りに余裕がなくAI活用まで行きつけない状況です。
横須賀:なぜ遅れているんでしょうか。
菅原:業務が劇的に変わらないことがあると思っています。契約書レビューがすごく早くなったとかリサーチ業務がゼロになったというところまで至っていません。さらに弁護士は完璧主義の人が多いので、カタカナ語は使わないとか語尾にこだわりがあったりと個性が文面ににじむので、AIが再現することが難しい。あとは単純に忙しい。大手なら専従で人をつけられますが、小さな事務所ではAIについて学習する余裕がありません。
横須賀:(自身が手がけるコンサルの)会員士業にAIについて教えていますが『自分にアポを入れる感覚でAIを勉強する時間をとってください』と伝えています。AIは使って感動しないと絶対使わないんですよ。社労士業界はどうですか。
三田:危機感がないことがあると思います。さらに社労士が自分の存在や経験を守りたいということがある。最近聞いた話ですが、AIが描いた絵と人が描いた絵、誰が書いたのかをいわずにアンケートをすると、ほとんどが「AIがいい」と答えるそうです。でも答えを言って再度聞くと、「人が描いた絵のほうがいい」となる。AIの進化は自分の存在意義を破壊するものだから価値が減るんです。AIに従いたくない気持ちは1つは自分を守るためなんじゃないかと。悩ましいですね。
横須賀:テクノロジーの進化で、明日仕事がなくなってしまうことは現実に起きていますよね。
三田:社労士で言うと「紙でやってきたからこそ内容が分かる」とか、「給与計算ソフト使っている人は、所得税引くときの引き算を分かっていないでしょう」とか、結構言われるんですよ。どう考えてもソフトのほうが正確なんですけれど。
横須賀:お客さんが気づいてきたら変わってくるんでしょうね。税理士業界ではどうですか。お客さんからクラウド会計でと言われたら対応しなければなりませんよね。
朝倉:実は、お客さんがクラウド会計を入れてほしいと言っても断る事務所もまだ多いです。弊社は税理士向けにDXコンサルティングもしていますが、freee(フリー)や「マネーフォーワード(MF)」の活用だけでなく、RPAやAPI連携を使ってkintone(キントーン)などで完全自動化するというような事務所は数%しかありません。一方で、手書きの書類や帳票をデータ化するニーズは多い。紙がメインの事務所がいきなり完全自動化は無理で、デジタル化の経験値を上げていくことが必要です。
AI導入が事務所経営を左右?「若い世代の採用に劇的に効く」
横須賀:みなさんの会社や周りではAI導入や活用をどう進めていますか。
三田:小さい事務所にとってAI導入はチャンスでしかありません。僕もすぐ飛びつきました。ただ、AIに詳しい人材の採用が難しくなっているので、自社で育てていくしかない。育てやすいのは学生です。知り合いのスタートアップでも興味のある学生を入れて、“AI番長”にしています。
朝倉:うちは9年目ですけれど最初からペーパーレスで、マーケティングもオペレーションも採用もなんでもデジタルです。士業の先生が個人的にデジタル化を進めることと、経営側に立って仕組的にデジタル化を進めていくのは全く別だと思います。士業は仕事が好きな人が多いと思うんですけれど、経営者になったときにはデジタル化が必要で、士業と切り分けて考える必要があると思うんですよね。うちはAIを専門にやってもらう人を採用しました。兼業だと進みませんから。
菅原:弁護士事務所の場合、AI導入は採用には劇的に効きます。若い世代は大学やロースクールでAIを使ってきているので、事務所がAI活用に前向きに取り組んでいるのは重要だと思います。若い人のほうが感度が高いので、一緒に作り上げる面白さもあります。
「まずグーグル検索をやめてChatGPTに聞いてみること」
横須賀:士業が身につけたほうがいいスキルは何だと思いますか。
三田:生成AIコンサルタントになることです。税理士が税理士に教えるレベルになるにはすごく大変ですけれど、生成AIは3カ月勉強するぐらいで教えられるようになってタイパがいい。国家試験を通った士業の方なら大丈夫ですよ。AIを使いこなすためのコツは、AIは自分より賢いことを認めることで、これが今日一番伝えたいことです。
横須賀:新しい技術はスタートが一緒ですからね。AIを学びたいという人には、「毎日AIに触って好きになること」と伝えています。ChatGPTにキャラ設定をすると会話が楽しくなりますよ。
三田:AIが人よりも賢いことを認めたうえで、士業の役割を考えると、人とのインターフェースであることですね。サービス提供するときに、インターフェースを人にするか、システムにするかの議論があります。さっきの絵の話と一緒で、全く一緒の情報でもAIと人間とでは、受け取る価値が違う。
横須賀:あるITサービス会社でも、顧客の問い合わせは全部電話で受けるそうです。チャットボットがやると満足度が下がりますから。AIをこれから使い始める人は、なにから手をつけたらいいと思いますか。
菅原:まずグーグル検索をやめてChatGPTに聞いてみることです。アポがある相手や会社情報を聞くとこんな情報があったのかと驚くはずです。ポイントは法律業務へのAI利用が現状の本丸ではないところで、生成AIに触りリテラシーを上げていくこと。技術が追いついたときに、本業でいかせるようになっておくことです。ChatGPTやAIが少し使えると業務フローの見直しにもつながります。
朝倉:ビッグデータが大事なので、社内の情報をためています。お客さんとのやり取りや、スタッフとのレビューメモといった細かな情報です。
AI時代に士業が取り組むべき方向性「データにないものを蓄積する」
横須賀:AIと人の業務のすみ分けができたときに、士業はどんなスキルを伸ばして、何をしたらいいと思いますか。
三田:法律や知識、思考の深さは完全にAIに負けるので、インターフェースとしての価値をどう高めるかだと思います。1つは誰が言ったかという「権威性」。この人の言うことなら正しいと思われる権威です。もう1つは「経験」です。AIは全て知識なので、経験を持ちません。でも経験がある人は説得力があります。あとはネット上にないデータをためることです。お客さんとの会話データや、税務調査が入ったときにこの調査官が厳しかったとか。グレーゾーンのデータは価値があります。
横須賀:生成AIは一般化するので、基礎的な情報と有名な話は出てくるけれども、中間の知識が意外とないんですよね。だから本を読むことが大事だと思っています。売れていない良書はデータベースにならないので。
菅原:データにないものを蓄積するというのは刺さりますね。弁護士はお客さんから情報を引き出すことが重要な仕事です。お客さまが大事と思っていなくても法的には大事だったり、法的に大事ではなくてもこの周辺も聞こうとか、さまざまな糸口を見つけて紛争解決に至ります。感情のもつれをひもとき、法的構成を組み立てることは当面、人間がやらなければなりません。文献のリサーチや文書作成はAIのほうが圧倒的に早いけれども、紛争を起こした人の奥底の感情を、どんな法的構成でもっていくかは人間がやらないといけません。プロフェッショナルが使って修正を加えて、初めて完璧な価値が出ます。
横須賀:お客さんはChatGPTに相談できるけれど、自分で気づかない質問はできない。そこを掘るのがプロの領域ですね。
菅原:クライアントの要求が当初のものと違うことがありますが、これを矯正する力はAIにはまだないですよね。AIがサジェストしない全体の1%しかないようなものを提案することに士業の価値があると思うし、逆にそれができないとダメなんだろうなと。
朝倉:士業しか持っていない情報というのは価値がありますね。今までは士業が持っていたのは知識でしたが知識は一般化していくなかで、士業しか持っていない情報は価値があります。お客さんの趣味嗜好やタイプが違う中で、人間が士業しか持っていない情報を活用していくイメージですね。
レアな存在であり続けるには?「人間力を磨く」「勝負する分野を熟慮」

横須賀:三田さんから権威性という話が出ましたが、そういう存在になるためのヒントはありますか。
朝倉:AIを活用してお客さんに価値提供することだと思います。AIは組織内の業務効率化に使うことが多いですよね。もちろんスタッフの業務負担軽減も大事ですが、お客さんにこの事務所がどう価値提供するかということを忘れずにやっていきたいと思っています。
菅原:トップランナーの方は今の業務で権威性を持っている方も多いでしょうし、そのままでいいと思います。ただ、権威性のある先生は忙しいので、AIを使うことでできた時間を、新しいことやなどに使うことができると思います。忙しすぎると人間らしさも発揮できないし、平たい言い方をするとAIが人の余裕をつくるわけですよね。
三田:レアな存在になることだと思います。みんな「優秀であること」を目指しているんですね。プロフェッショナル集団の中で、権威性を持つのは大変です。レアな存在になるために、どの領域で勝負できるかを考えたほうがいいです。例えば運送業に強い、エンタメ業界に強い社労士というニッチを目指すイメージです。
横須賀:どうすればレアな存在になると考えますか。
菅原:AIにない人間力を出していくことでしょうか。お客さまは皆さんの個性に惹かれて来てくれるので、自分のキャラを磨いたり発信したりすることかと思います。全員が三田先生のようにはなれないんで(笑)。この業界でやっているある程度の年代の方なら「最近、うちで生成AIを使い始めました」と言うだけで、すごくレアかもしれません。
朝倉:どこに対してレアかということですよね。小規模な事務所は、ニッチな専門分野で独自性を出す戦略が必要だと思います。でもテクノロジーの進化や、大手資本の算入で、将来的に希少性がなくなってしまうかもしれない。以前は、AIに精通した税理士に他の税理士の仕事が奪われると言っていたんですけれども、最近は、税理士業務に関係ない大手資本が、持っている情報に目をつけて入ってきて、デジタルに強くない事務所と組む、みたいなこともありえます。どの分野で価値を提供し続けられるか、戦略を立てることが大事ですね。
AI時代の人材採用と育成「生身のトレーニングまだまだ必要」
質問者①:菅原さんの話で生成AIが3年目のアソシエイトレベルまでになっているとありました。社会人になったばかりの人は、3年目までの経験をどう積むのでしょうか。
菅原:AIが先生になるというのが正解かと思いますが、うちの事務所でもまだ仕組み化されていません。これまでOJTでやってきたことを教え込む必要はあります。一方で経験が3年ないと到達できないということではなく、AIに方法をインプットしておけば、3年より早く到達できると考えています。1年目と3年目の違いは、知識量と問題発見能力だと思っていて、ある事案を聞いたときに何が問題になりそうかを考え、ChatGPTに何を聞くのかが1年目と3年目では変わってきます。もう一つはデータ化していない情報、クライアントの担当者の特性などを学ばせることですね。技術面と経験面を同時にアップデートするトレーニングをする必要があります。生身のトレーニングが必要なものがまだまだあります。
質問者②:社内のAIに対する温度差はどう解消していますか。
朝倉:言い続けることかと思います。うちもコードを書けるメンバーは数人で、それを一般よりも多少リテラシーが高い人が使っています。社会ではいずれ機械に代替されることをやっていきたいという職人気質の人が多数な気がしていて、そうした中で採用は大事です。変化に挑戦したいというマインドの人を採用して、人材育成でAIを社内文化にします。
菅原:まだこれからですが、トップランナーやフロントランナーの人が引っ張ることが必要です。AIが日常業務の中で溶け込んでいる状態を目指したい。毎日使うパソコンのトップ画面にAIを入れるなど、使ってもらえる工夫を重ねることで、浸透すると考えています。
三田:人事評価を変えることが1つかなと思います。ある大企業で、AIの研修をしたのに大半の人が使っていなくて、理由を聞いたら評価が上がらないと答えたと。生成AIで自分の業務が減ったら別の仕事がくるのではやる気が起きません。人事評価を変えてもいいんじゃないでしょうか。
横須賀:うちの事務所は、(1)危機感をあおる、(2)社長である自分が使いこなす、(3)給料を上げるですね。社内の温度差を解消するにはトップ自ら取り組むことだと思っています。
【プロフィール】
朝倉歩(あさくらあゆむ)
サン共同税理士法人CEO[税理士]
1979年生まれ。約12年間、デロイトトーマツ税理士法人にて実務経験を積んだのち、2016年にサン共同税理士法人を設立、代表社員に就任。職員数120名以上、全国に10拠点を有する法人に成長。2019年、サン共同デジタルコンサルティング株式会社を設立し、自社開発システムやRPA等、最新のDXで会計事務所業務の効率化に注力している。
菅原稔(すがわら みのる)
AZXProfessionalsGroupマネージングパートナーCOO[弁護士]
弁護士登録後、AZXにて一貫してスタートアップ企業・VCの法務サポートに従事。2016年には株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社)へ出向、2018年AZXパートナー、2019年同マネージングパートナー就任。VCにおける業務経験を活かし、スタートアップ側・VC側双方に対して、投資スキーム(種類株式、J-KISS、CB等)、投資契約書等に関する助言を行う。また、大学発ベンチャーの創業支援、大企業における社内ベンチャー制度の支援など、自らの経験を生かした非典型的な領域も多く手掛ける。
三田弘道(みた ひろみち)
株式会社HRbase代表取締役[社会保険労務士]
大阪大学大学院卒業。在学中に社労士の資格を取得し、人事労務支援を行うベンチャーに入社。2015年に株式会社Flucle(2024年11月に株式会社HRbaseに社名変更)を設立。企業の労務管理支援で感じた課題をもとに、HRbaseサービスを展開。労務アシスタントAIの開発に取り組んだ。
横須賀輝尚(よこすか てるひさ)
パワーコンテンツジャパン株式会社代表取締役[行政書士]
専修大法学部卒。在学中に行政書士試験に合格、23歳で事務所を開設。約1年で年商1000万円を突破した。「法律実務家の新しい未来をつくりたい」との考えで、2007年に日本初の士業向け経営塾「経営天才塾(現LEGALBACKS)」を創設。行政書士にとどまらず幅広い士業向けにマーケティングなどを指南している。
【お知らせ】
「士業DX白書2025」では今回の登壇者が全員登場。このほか、弁護士、税理士など7士業を横断した、DX期待度スコアの算出、士業ごとの概要・課題分析、士業やそのユーザーのアンケート、DXサービスリストの作成など、多岐にわたるコンテンツを掲載しています。PDF版を無料で配布していますので、ぜひご一読ください。
詳細はこちら