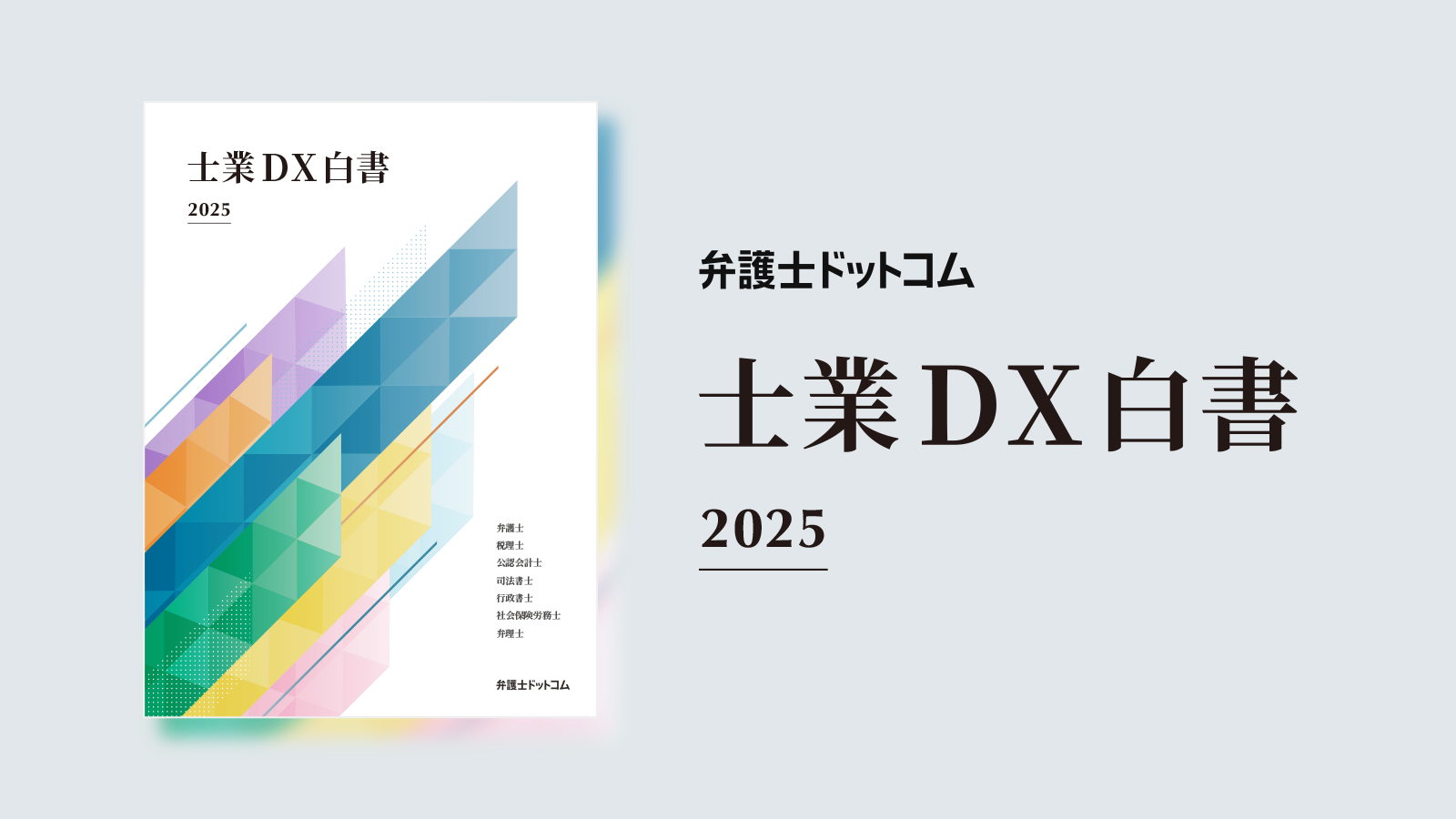冨山和彦氏が語る、AI時代に士業が飛躍する条件 「こんなに面白く刺激的な時代はない」
士業の専門的知見やスキルはAIに代替される、と言われるようになって久しい。生成AIの登場によって、ますますその可能性が高まってきたと言えるだろう。 しかし、それは士業の仕事がAIに置き換わってしまうかもしれないという懸念である一方、AIの活用で仕事のあり方を変えることのできるチャンスでもある。 AI時代に士業が飛躍するための条件は何なのか。大学在学中に司法試験に合格、経営コンサルタントとして長年活躍してきた冨山和彦氏は「自己変容ができる士業にとって、こんなに面白く刺激的な時代はない」と断言する。 AI革命によって、オフィスで働くホワイトカラーの仕事がブルシットジョブ(どうでもいい、無意味な仕事)となり、ホワイトカラーが行き場を失っていると、著書『ホワイトカラー消滅』(NHK出版新書)で説く冨山氏に、時代の変化と士業DXのあり方を聞いた。 文:荻野進介/企画:新志有裕/写真:永峰拓也 (士業DX白書2025、弁護士ドットコムタイムズVol.74<2025年3月発行>より)
AIが書類処理で人間を圧倒しても、稚拙な問いには稚拙な答えしか出せない
生成AIが怒涛のように進化、浸透する中、それと競合するような分野の士業の仕事は生成AIに代替されざるを得ないでしょう。具体的にいえば、新しい法律や通達、最新の知識などに関する書類処理業務で、それらはすべてAIが365日、24時間かけて読み込んでいるわけです。人間がかなうはずがありません。
そうではなく、人間はAIを使う立場にまわるべきです。AIの興味深い点は、稚拙な問いに関しては稚拙な答えしか出せないところです。こちらが素人だと質問の回答に対し、さらに質問を重ねることもできません。逆にいえば、自分が生成AIに何を求めるかをわかっていて、質問の仕方に工夫を凝らすことができる優秀な人ほど、AIを使いこなすことができるのです。
士業事務所の経営者からすれば、AIの導入により、仕事の生産性をアップさせることができます。今までは下働きをするアソシエイトが数人必要だったところ、1人か2人で済むようになる。何冊もの法典や分厚い判例集も不要になり、その分の経費も浮くことになるのです。
どの士業でもそうですが、AIを使える人、使えずに代替されてしまう人といったように、人材格差が大きく開くことになるでしょう。
では、代替されないためには、どうしたらいいのでしょうか。AIが対応できない能力に磨きをかけることです。先ほど「問い」の話をしましたが、もう一つ、AIが対応できないのは「物事を判断すること(Judgement)」です。判断というのは、裁量性があって、リスクの高い業務ほど不可欠です。
たとえば、経理文書で何を貸方に置き、何を借方に置くのか。これは会計士によって判断に幅があります。事業の継続性という場合も同様です。AIに尋ねると、「この場合は……」というように、条件付けをしてくるはずです。最後は分からないので、人間のあなたが判断してください、というわけです。
短くなる若手の見習い期間 深い思考力を培うことに使えばいい
士業を目指す若者にとってはチャレンジングな時代になったと言えるでしょう。今までは資格試験に通って事務所に就職し、5年から10年、15年、アソシエイトとして修行を積み、そこからマネジャー、パートナーになるというのがキャリアの王道だったのが、その修行期間の仕事の多くがAIに代替されてしまう可能性が高くなりました。マネジャー、パートナーの仕事は変わっていないわけですから、AIに代替される可能性が高いこの修行期間をいかに早く駆け抜けるかが非常に重要になります。
裏返していうと、先述したように、AIを使う側になるための勉強が必須になります。法律事務所には以前、スーパー・パラリーガルと呼ばれる、司法試験には通らなかったけれど、判例を読み解かせたらピカイチといったスタッフがいたものです。こういう人がAIの浸透によって要らなくなります。半面、AIには身体がありませんから、現場に行って証拠を調べる捜査員のようなスタッフは重宝されます。
見習いや修行の時期を早く駆け抜けられたら、若者にとってはいい時代になると思います。見習いの時期に暗記しなければいけないことが減ります。当然、仕事の時間は短くなり、空いた時間で広く、深い思考力を培うことができます。弁護士でいえば、リーガルマインド(法的思考能力)の醸成をすることができるのです。
もちろん、弁護士だからといって法律の世界にだけ通じていればいいわけではありません。政治学、経済学、社会学、場合によっては、芸術の知識といったリベラルアーツが不可欠です。リベラルアーツは究極の判断能力ともいえ、「答えのない問いの世界」ですから、誰かに学ぶというより、自分で主体的に育み、身に付けていく必要があります。
リベラルアーツとは、世の中の森羅万象に好奇心を持ち、それらを観察しながら、独自のインスピレーションを得、それに付随した社会的仮説を持ち、事実で検証していく。つまり、「問いを立て」「答えを模索し」「決断する」というサイクルを日常的にまわす力といっていいでしょう。だから真のリーガルマインドとかなり重複します。この力があれば、AIには絶対に代替されませんし、どんな業界でも十二分にやっていけます。
半面、AIはリベラルアーツとは対極の各分野の専門能力に非常に長けています。たとえば、私の父親は日系カナダ人二世なのですが、これに関する国籍の問題などは外務省に聞いても駄目で、法律事務所に尋ねたら法外な金額を要求されてしまう。そこでAIを使ってみたところ、すぐに判明しました。
また、論文を書くときは新規性をチェックするため、その分野の過去の論文を隈なく読むことが必要ですが、AIを使えばその過程が大幅にスキップできます。2024年10月に出した新刊『ホワイトカラー消滅』もAIに調べものを任せることで、随分と労力が減りました。
さらに、ある問題について、冨山は何を言っているか、マッキンゼーはどう言っているか、ボストンコンサルティングはどうか、ということまで、AIが明らかにしてくれる。こうしたAIの力には驚くばかりです。
このAIと競合するのは大変です。専門に閉じこもらず、AIをどんどん使い倒していけるか。リスキリングですね。それができるかどうかが、若手を含めた今後の士業人材の行方を占う試金石になると思います。
コンサル志向を強める士業 専門領域の壁を超えてこそ活躍の余地あり
士業の世界で勝ち組になるにはその分野のコンサルティングをできるようにならなければいけないとよく言われますが、言うは易しですが、実行は難しい。
たとえば、クライアントから「親が亡くなったから、相続税を最少化したい」と、税理士が言われたとすると、その業務はAIに簡単にやらせることができます。
ところが、「税金を減らす一方で、事業承継を確実に行いたい」というケースの場合は話が変わります。それこそ、生身の税理士が担当し、相手の要望をうまく汲み取りながら、業務を遂行する必要があります。事業承継を安定的に行うには、相続税を安くするための有効手段となる持ち株を減らすことをやらないほうがいい。なぜなら株を分散させるとガバナンス力も分散し、お家騒動の種になってしまうからです。それまで、いくら仲のよい兄弟であっても、骨肉相食む“争族”となりかねない。
それを防ぐには、それこそ人間に対する深い洞察が必要で、AIはまったく対応できません。これこそが税務コンサルティングです。税法をいくら暗記するより、シェイクスピアの『ヘンリー五世』でも読んで、「人間とは何か」に対する学習をするべきなのです。
もう一つ、コンサルティングというのは専門領域を出ることですが、それもなかなか難しい。士業の世界には専門領域の壁があって、弁護士、会計士、税理士、それぞれが各自の殻を破れない。他の士業の専門領域を侵さないというのが暗黙の前提になっています。
でも、その専門領域を少しはみ出たクロスオーバー領域にこそ、AIが決して対応できない、生身の士業が活躍できる余地がたくさんあるんです。
たとえば、弁護士と税理士の資格を合わせ持つ人は少ないですから希少価値がありますし、弁護士と公認会計士の資格を持っている人も企業再生などに抜群の力を発揮します。弁護士と社会保険労務士も意外な組み合わせでお勧めです。
どんなに新しい世界でも通用する「そもそも論」を学ぼう
弁護士が税理士の資格を取るとしましょう。リーガルマインドを持っていると、同じ法律ですから、税法の理解も難しくなく、税の原理原則を比較的簡単に把握することができます。
法人税という税があります。そもそも論をいうと、法人税の歴史は新しい。というのも、人類の歴史においては法人というものは長く擬制であり、フィクションと見なされてきたからです。法人擬制説の立場に立つと、法人税は個人の所得税と二重課税になるから、憲法違反だという意見があるくらいです。その法人税が各国で成立したのが戦争の多かった20世紀で、目的は戦時の代替徴収でした。家長たる男は兵隊に取られているから課税ができない、代わりに法人に課税しようとなったんです。
こうした物事の出自を探る「そもそも論」が物事の深い理解にとても役立ちます。リベラルアーツそのものといっていいでしょう。会計もそうです。そもそも複式簿記は何のためにあるのか、そもそも財務情報の開示は誰の利益を図ってのものなのか。そうしたそもそも論が集まったところに、会計の諸原則がある。法務や税務、社会保障も同様です。
士業というのは輸入学問で成り立っています。西洋の法制度に基づき、日本で制定した継受法で成立している。その元では、そもそも論は無視され、所与のものとしてスタートする解釈学が主流となっています。別の言葉でいえば、継受法イコール解釈学であり、制度設計学、立法政治学といった法律のあり方を一から考える学問が日本で未発達なのもそのせいです。
そもそも論は本来、大学で教えるべきですが、現状ではそうなっていません。大学でそもそも論をやると、「立法論に逃げ込むな」と言われます。あくまで、既成の法律の枠組みで、具体的妥当性を考えることを求められるのです。
でも、それをやっている限り、ルール・メイキングを行う国際競争に勝てません。日本がその分野に弱いのはそもそも論に長けていないからです。
そもそも論をやる人は改革志向が高まりますが、それをいくらやっても、日本の法学の頂点に立つ東京大学の法律の先生にはなれません。日本の法学者は法改正を嫌います。2020年、約100年ぶりに民法が改正され、それを主導したのが東京大学法学部教授(当時)の内田貴先生でしたが、それは内田先生が大民法学者という評判を先に獲得していたからできたことでした。
AIはこのそもそも論を理解していません。AIに対抗していくためには、そもそも論を学ぶ必要があります。自らが立法者だったら、あるいは制度設計者だったらどう考えるか。これを思考の基軸におくことです。
ある資格を持っている人が新しい資格を取得しようとするとき、そもそも論を理解していると、より簡単に新しい領域に入ることができます。法律にも会計にも税務にも、共通項があり、それにはそもそも論が濃厚に関わっているからです。弁護士資格を保有している人が会計の世界をいちから勉強するのは大変な労力を伴いますが、そもそも論を理解していると、その世界に簡単に跳ぶことができます。「冨山さんは活動領域が広い」とよく言われますが、そもそも論に長けているからではないかと思っています。
大学に行かなくても、基礎法学や税の歴史などの本を読んでいけば、そもそも論を学ぶことは可能です。読むべき本、読みたくなる本がどんどん増えていくはずです。
生成AIで調べさせてもいいでしょう。最近、そのAIで知ったのですが、かのローマ法にも既に債権者取引法があったことがわかりました。以前は図書館に通わなければできなかったことが、家にパソコンがあり、ネットにつながっていれば、事足りる世の中になり、とても便利になりました。
知的好奇心に駆られ、そもそも論を追っていくと思考が遠回りする印象がありますが、士業の専門知で生き残るためには欠かせないことだと思います。
ホワイトカラー消滅時代は「個の時代」 士業が貢献できる領域も広がる
熾烈なグローバル競争に勝つために、グローバル企業のホワイトカラーの仕事の多くがAIに代替され始めています。ホワイトカラー中間層の時代は終わり、ホワイトカラーは二極化します。
ホワイトカラーに残るのは本当の意味での経営の仕事、つまり「ボス仕事」です。これまで数多くあったホワイトカラーの「部下仕事」はAIに急速に置き換わっていきます。ボス仕事ができる人、部下仕事しかできない人に分化します。前者は要る人になり、給料が上がり、後者は要らない人になって給料が下がるでしょう。
その次に起こるのは、グローバル企業で部下仕事しかできなかったホワイトカラーから非ホワイトカラー職種、具体的には、ローカル企業のエッセンシャルワーカーへのシフトです。エッセンシャルワーカーとは、人々が日常の生活を維持するために欠かせない職業を指し、具体的には医療、介護、交通、インフラ、物流、公共サービス、小売、農水産業に従事する人たちです。ホワイトカラーが余っている一方で、こちらは深刻な人手不足になっています。シフトするためには、リスキリングが必要になります。
そのとき、エッセンシャルワーカーが労働生産性の高い、高度化、進化した「アドバンスト・エッセンシャルワーカー」に変容できるかが大きな鍵を握ります。既にアドバンストになっている例が、ホワイトカラー的意味合いを持ちつつ、デスク外で仕事をしている医師であり、パイロットです。
先述のように、ホワイトカラーが分化する結果、企業も大きく変わらざるを得ません。その一つとして、税務、法務、社会保険といった、社員向けの企業の代理業務がなくなることが予想されます。その背景には、一身丸抱えのメンバーシップ型に変わり、仕事でのみ会社と結びつくジョブ型雇用の浸透があるでしょう。
今まで会社任せにしていた税の申告や社会保障の支払い業務を自分で処理せざるを得ず、士業のマーケットが大きく広がることが予想されます。半面、士業の中でも位の高い弁護士や会計士はそのハードルをぐっと下げざるを得なくなるでしょう。結果、各士業において、クライアントのニーズを探り、適切な事務所にクライアントを誘導する、医者でいうところの、専門医を紹介する入り口となる「かかりつけ医(総合診療医者)」がいないことが大きな問題となります。
そのかかりつけ医に最適なのが、先ほどからお話しているAIなのです。士業というのは法化社会の賜物です。弁護士、会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、弁理士は、それぞれ民法、行政法、会計法、税法、労働法、弁理士法があって、初めてその存在が許されます。逆にいえば、各法律に依拠した縦割り構造のもとで成立しているために、ある相談を実際の事務所に振り分ける総合診療的な「かかりつけ医」がいないのです。
たとえば、相続税の支払いについて、法律事務所に聞いたらいいのか、税理士事務所がふさわしいのかを正確に答えられる一般人は少ないはずです。そのかかりつけ医の役割をAIが担うことができれば、エッセンシャルワーカー個人の権利を守るだけではなく、そこにサラリーマン以外の一般人も容易にアクセスできます。士業に対するハードルを下げ、法化社会における一つのアクセシビリティをAIが担うことができるのです。
観光ツーリズム産業で起きる「元ホワイトカラー」と士業の新たな関係
では、部下仕事しかできず、企業に見切りをつけられてしまったホワイトカラーはどうすればよいのでしょうか。
実際のところ、司法書士や社会保険労務士の資格を新たに目指す中高年も増えているようですが、経営の仕事を担うことができない人材が士業の世界に来ても、早晩AIとの戦いを強いられることになり、あまり意味がないのではないでしょうか。少なくとも給料が上がる感じがしません。
私は年齢不問が圧倒的に多い日本各地の中堅中小の観光ツーリズム業のマネジメントに入るのが一番いいと思います。交通インフラ、農林水産、飲食宿泊、社会インフラなどです。日本の雇用人口は約7000万人おり、そのうち最も数が多いのが自動車産業で約550万人、その次が観光ツーリズム業で500万人。好調なインバウンドを背景に、早晩、1000万人を突破し、日本で最も雇用者の多い業界になると言われています。
そうした企業はいわば「田舎の駅長さん」で、法務、税務、経理はもちろん、労働基準監督署の対応から施設の衛生管理、帳簿付けまで、すべて一人で対応しなければなりません。自分でできなくても、弁護士や社会保険労務士、税理士と対等に話せる能力が必要です。グローバルで通用しなくなったホワイトカラーがそんな経営者の片腕となったらいいのではないでしょうか。
資格試験はこのままでいいのか 変化するジョブを再定義すべき
AIの発達により、士業の資格試験も変わらざるを得ません。今までは知識を試すテストが圧倒的主流でしたが、それはAIに任せればいいので、ナンセンスです。
士業というのはソフトウェアの世界とよく似ています。ルールを基礎に動くアルゴリズムの世界です。そのアルゴリズムの部分は確実に生成AIにとって代わられますから、資格試験の性格を変えていかざるを得ません。本来、試験とは通った人がその資格でご飯を食べられるようにするためのものであるべきですが、今はそうなっていない。試験に通ったけれども、実務に使えないという状態は嘆かわしいの一言です。
たとえば、社会保険労務士の資格試験があります。現状は労働法の中身を細かく聞いていくものが主流ですが、実務に出ると、そうした机上の知識よりも、クライアントたる企業の経営者や人事に寄り添うことが大切なのです。
試験内容と実務が遊離しているわけですが、社会保険労務士におけるジョブとは何か、という定義が明確になされていないことが大きい。
社会保険労務士のジョブには、具体的労務問題に対処するうえで、相手の心を解きほぐすための対面スキルや臨床心理士的な知識、本当のことをなかなか明かさない相手の心理を探るマーケティングのスキル、相手の知識や知能に応じて中身を変える語彙力、話を傾聴し適切なアドバイスを下すカウンセリングのスキルが必要で、それらヒューマン・スキルを社会保険労務士の資格試験にも組み込むべきなのです。
試験時にAIを使わせる科目があってもいいでしょう。士業におけるスキルセットを変化に応じて変えていく。人間科学も日進月歩で発達しますから、その成果を大胆に取り入れていく。これは社会保険労務士に限らず、すべての士業に当てはまることです。
ジョブをどう定義したら、クライアントがお金を支払ってくれるか。それを日々、どうリファインしていくか。それを国に丸抱えさせず、弁護士なら弁護士会、公認会計士なら公認会計士協会がしっかり対応するべきです。
ヒューマン・スキルを磨いて自己変容を続けることが大切
何らかの非対称性でビジネスが成立しているという意味では、士業もコンサルティングファームも構造は同じです。相手が持っていない知識を保有しているという「知の非対称性」、相手が巡り合ったことがない状況を知悉しているという「状況の非対称性」、相手が経験したことがないという「経験の非対称性」、この3つでビジネスが成り立っています。この知の部分がAIにどんどん代替されようとしているのが今です。状況や経験の非対称性がますます重要になりますから、すべての士業はヒューマン・スキルを磨かざるを得ないのです。
現代の日本のスポーツがまさにそうなっています。教える(Teaching)から指導する(Coaching)へ、体系が大きく変わりました。この転換の背景にあるのが、教えることを徹底してしまうと、試合中に選手がベンチの監督を見るようになってしまうという弊害が生じてしまうことです。それでは試合に勝てない。そうではなく、各選手を指導し、いいところを引き出す。間違いを自分で改めさせる。今やあらゆるスポーツで、このコーチングで育った世代が次々に台頭し、オリンピックなど数々の国際舞台で大活躍しています。
企業と比べると、士業の世界は難しい筆記試験に頼り過ぎです。企業は18歳のときに学力がピークで、大半がそこから落ちた大学の新卒生を採用し、数年かけて一人前のビジネスパーソンに仕上げていきます。一方の士業は、たとえば法律事務所の場合、試験を通ったばかりの一年生を平気でクライアント業務に就かせ、使えないと文句を言っている。企業人から言えば何を甘えたことを、と言わざるを得ないでしょう。
試験とは最低限の“品質保証”に過ぎません。それに合格しているということは、士たる必要条件にしか過ぎません。それを育て、教えて能力を高め、必要十分条件にまでして、はじめてクライアント業務に就かせることができるのです。
「AIは間違えるから、けしからん」という人が各士業の幹部の中にもいます。でもAIと言うのは人間を模したもので、いわば人間の“写し絵”に過ぎない。つまり、人間だって間違えるのです。ところが人間は故意に間違えますが、AIには故意がありません。
AIが各士業の仕事に、さらに企業にも入り込んだうえで、ホワイトカラーが二極化し、それに対応するため、士業の重要性が増す。自己変容ができる士業にとって、こんなに面白く刺激的な時代はないと思います。
【プロフィール】
冨山和彦(とやま・かずひこ)
1960年東京生まれ。東京大学法学部卒業、スタンフォード大学経営学修士(MBA)。司法試験には東京大学在学中に合格。ボストンコンサルティングを経て、産業再生機構のCOOを務めるなど数多くの企業の経営改革や成長戦略に携わる。2007年4月に株式会社経営共創基盤(IGPI)を設立、代表取締役就任。2020年10月よりIGPIグループ会長。日本取締役協会会長。
【お知らせ】
冨山氏のインタビューを含め、「士業DX白書2025」では、弁護士、税理士など7士業を横断した、DX期待度スコアの算出、士業ごとの概要・課題分析、士業やそのユーザーのアンケート、サービス開発者インタビュー、DXサービスリストの作成など、多岐にわたるコンテンツを掲載しています。PDF版を無料で配布していますので、ぜひご一読ください。
詳細はこちら